みんな月に行ってしまうかもしれない
「ここにはそんなに長くいないかもしれないから」と彼女は言いにくそうに言った。「みんな月に行ってしまうかもしれない」と私は言った。彼女はよく聞き取れなかったようだった。「今、なんて言ったの?」「なんでもないよ。たいしたことじゃない」
騎士団長殺し/ 2章/ 村上春樹
昨年の秋、私の状況は最悪だった。腰痛持ちのお爺さんがフィギュア・スケートに挑戦した時のように、全ての行動が(ひとつの例外もなく)悲惨な結果を招いた。仕事をすれば顧客を失い、身体を鍛えればお腹を下し、贈り物をすれば不仲になった。自信と誇りが粉々に打ち砕かれた。運気を司る神々からも宿命的に見放されていたので、街を歩けばキックボードに撥ねられ、美容室に行けばちびまる子ちゃんみたいにされた。裏返された亀の方がまだ希望があった。
私は致命傷を負っていたが、それでもタフに立ち上がらねばならなかった。しかし動き出そうにも、足がもつれるほど状況は絡み合っていたし、無数の地雷も埋まっていた。そこで、一旦なにもかも手放すことにした。家を捨て、会社を潰し、街を離れた。住む家を失ったので、安楽死寸前のマニュアル車を購入し、そのなかに樫の木を組み立てて住まいを作った。仕上げに携帯電話の電源を落とし、頃合いの湖を見つけて投げ捨てた。連絡が取れなくなった者には申し訳ないが、月にでも行ったと諦めてもらうしかない。そうして私は車で暮らすようになった。
次に私は、承諾なしに憑いてきた疫病神を追い払う作業に取り掛かった。彼(あるいは彼女)は、陰湿で粘着質なストーカーのように、紳士的な説得だけでは決して離れようとしなかったので、私は車を走らせてまくことにした。海から山へ、町から街へ、毎日10時間も忍耐強く走り続けた。ガソリンを徒(いたずら)に消費して空気を汚していることには心が痛んだが、疫病神には確実に効果がみられた。ひと月も経つと、彼(または彼女)は、飢えた野良犬のように痩せ細り、憑いていくのがやっとという様子だったので、私は速度を控えてじわじわと追い込んだ。そうして悪霊は完全に消滅した。
除霊を終えると、私は肉体の疲労を取り除くために、奈良の十津川村で湯治を行った。湯に浸かりながら、これから描くべき創作に思いを巡らせたり、(短い時間だが旅を共にした)疫病神に哀悼の誠を捧げた。もうしばらく通信機器を手放し、ほとんど外の世界から隔離された生活をしていたが、滞在中に一度だけ、銭湯のテレビでNHKのニュースを(久しぶりに)見た。でもそこで伝えられた一連のニュースは始めから終わりまで、私とは何の縁も関わりも持たない、どこかよその惑星の出来事みたいに思えた。あるいは誰かが適当にでっちあげた作り事のように思えた。
「みんな月に行ってしまうのかもしれない」私はそう呟いた。
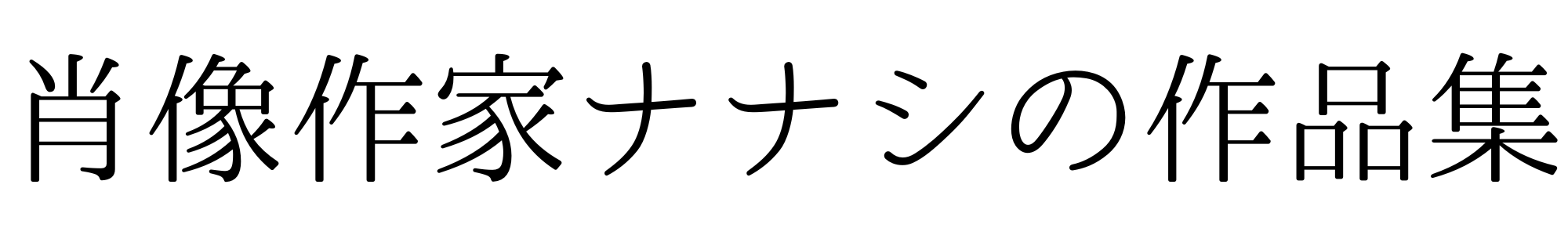
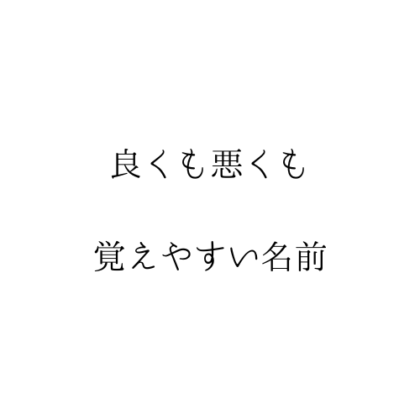
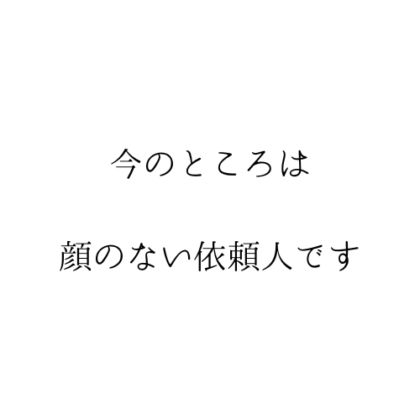
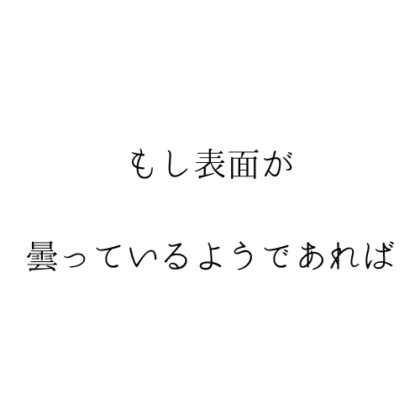

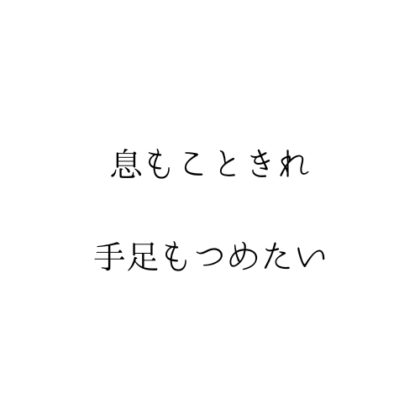
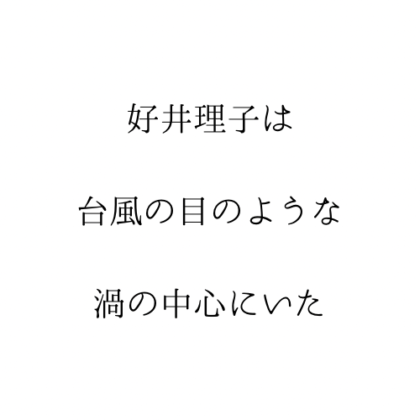
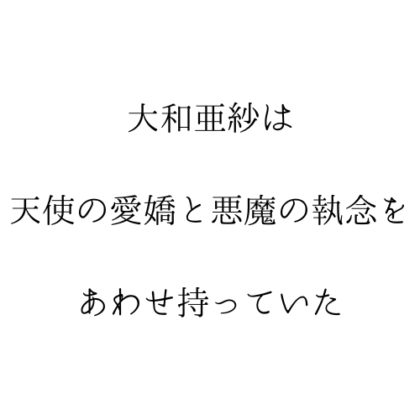
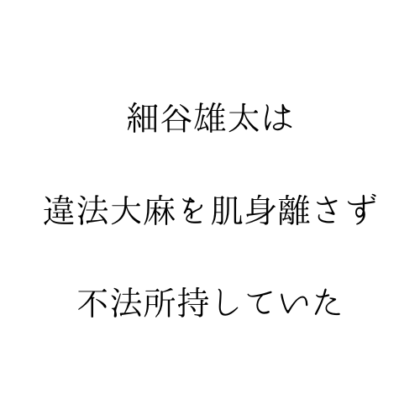
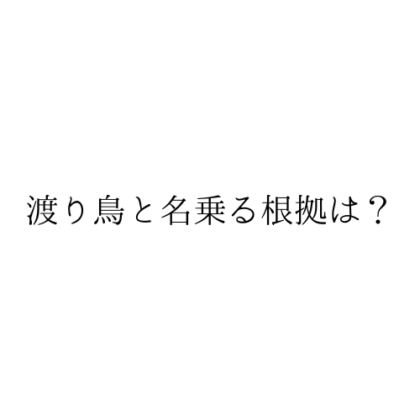

Leave a Reply