藤原なつみは距離感の尺度が常人離れしていた
藤原なつみは、距離感の尺度が常人からかけ離れていた。
なつみが口にする「ちょっとそこまで」は、ラクダに乗って丸二日ほど砂漠をさまよい、蜃気楼のむこうにようやく姿を見せるくらいの距離だった。彼女がいう「ささやかな寄り道」は、パリやニューヨークから成田に帰るまでに、マルタ島やワイキキビーチに立ち寄るようなものを意味していた。実際になつみは、ある月にコスタリカにいたのかと思えば、翌月にはカナダで暮らしていたし、また別のあるときには、カリブ海の船上から連絡がきたかと思えば、次の通知はオーストラリアで日光浴をしながらだった。そのおかげで私は、彼女に電話をするときには、まず経度と時差の確認からしなければならなかった。
なつみは幼いころから《走ること》に心を奪われていた。移り変わる風景の中で、風のことを考え、雲のことを考え、しかし本質的には何も考えずに空白の中を走る。そのような自分だけの世界に魅了された。はじめはちょっとしたジョギングからだったが、気づけば走るために寮で暮らし、大学への推薦を受け、実業団の選手に選ばれるほど、彼女の青春はそれ一色になっていた。南米に輸出されたトヨタ車のように、数千キロ、数万キロと走り続けたことで、彼女の距離感覚は桁数がひとつ故障してしまったのだ。
あの頃、周りの大人たちのなかには、なつみの生活を苦行のように捉える者もいた。蝉の鳴く夏や、氷柱が光る冬に外を走れば、「わざわざ苦しい思いをするなんて」とお節介を言われることもあったし、逆に「武士のように意志が強いんですね」と感心されることもあった。しかし彼女からすれば、走ることはただ性に合っているだけで、それほど苦痛だとは感じていなかった。
たとえば渡り鳥が「羽ばたくのって結構腰にくるんですけど、飛ぶしかありませんから」と不満を漏らすだろうか。カジキマグロが「泳ぎ続けなければ死にますけど、これも前世からの運命ですから」と嘆くだろうか。そんなことはない。少なくとも彼女は走ることが嫌いではなかった。だから体育の授業で、みんなが走らされている姿を見ると不憫に感じたし、学校で学べる最大のことは「大事なことは学校では学べない」のだと確信を深めた。
怪我をして、数年前に走ることは辞めたが、自分は四半世紀もの間、走り続けることができた。次に《続けられること》はどこにあるのだろうか。飛行機の窓から見える次の大陸を眺めながら、なつみは子どものころに出会えた宝物を再び求めていた。
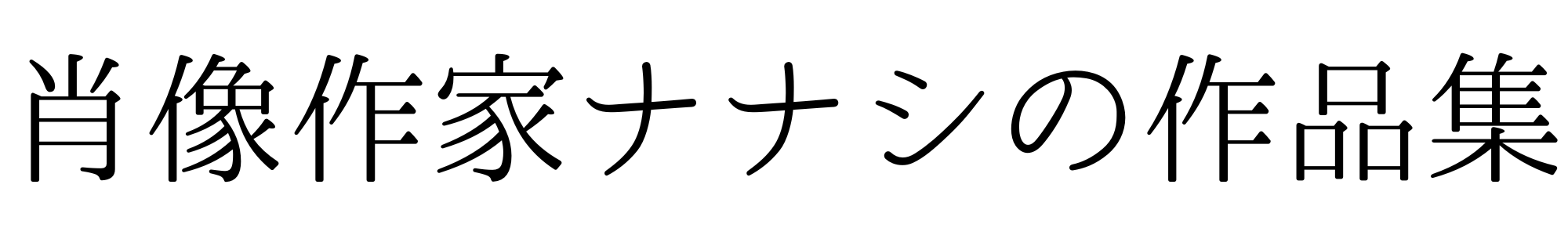
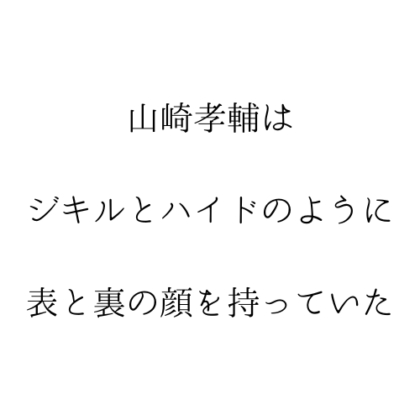
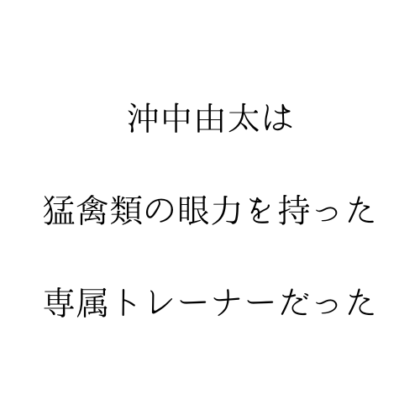

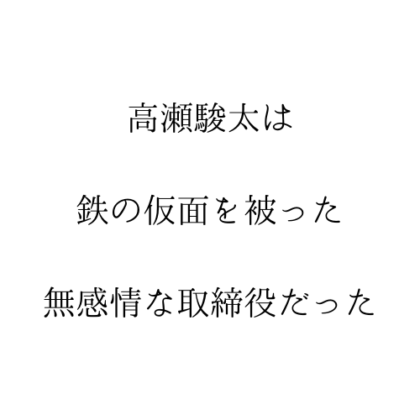
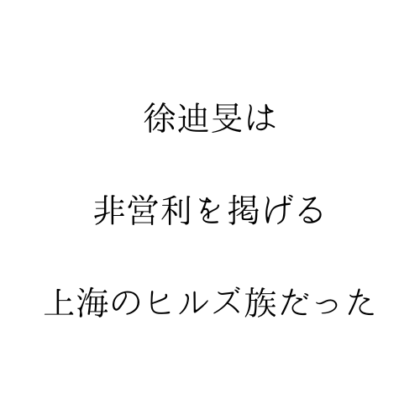
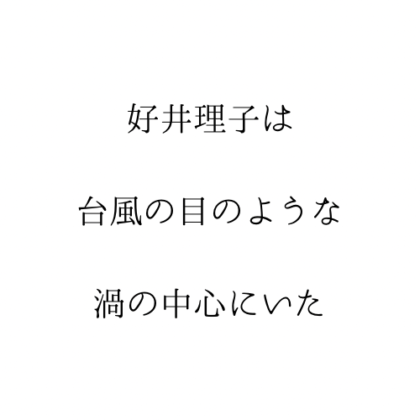
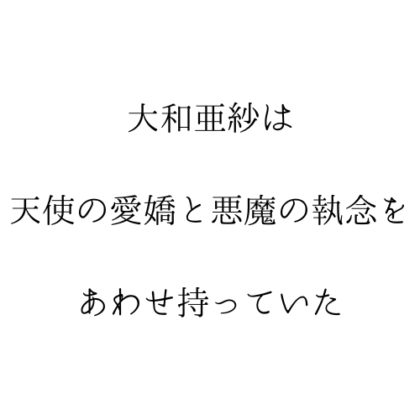
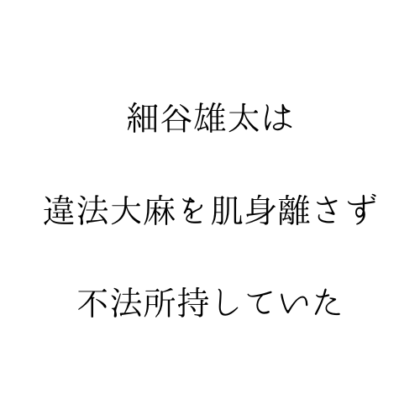
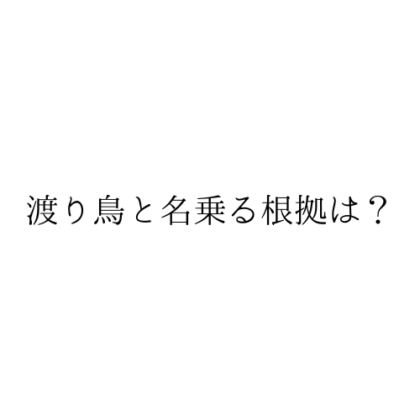

Leave a Reply