中村理沙子はあらゆるアレルギーを持っていた
中村理沙子は、あらゆる種類の鼻炎性アレルギーを持っていた。
彼女の鼻を刺激するものを並べると、星付きのレストランで渡されるワイン・リストのように、ちょっとした小冊子になった。
杉にひのき、稲・麻・よもぎと、1ダースを超える植物の花粉から始まり、ダニやカビ、犬・猫・うさぎと動物性へ移り、蛾の鱗粉や香水、月の満ち欠けに至るまで、その圧巻の品揃えには、誰もが舌を巻いて感心してしまうほどだった。
理沙子は生粋の都会育ちだったが、慢性的な鼻声だったため、その話し方にはどこか田舎臭さを感じるところがあった。たとえば、彼女が「どうしたの?」と相手を気遣う時には「どうしたど?」になり、待ち合わせに遅れたときには「おばたせしてごべん」になった。
読者諸君のなかには、一介の物書きがひとりの女性を語る上で、いきなり鼻炎の話題から始めるのは(倫理的に)いかがなものかと抗議を申し立てるかもしれない。
確かにその考えは常識的ではあるものの、私は彼女と数年の付き合いを経ても、未だかつて鼻炎でない姿を見たことがないため、もはや鼻詰まりの情報を持ち出さずに、理沙子の人物像を語ることは、ミッキーのいないディズニーランドで間を持たせるようなものである。
しかし安心していただきたい。魔女の呪いのような鼻炎があることを除けば、彼女はほとんど完璧な女性だった。まるで声を奪われた人魚アリエルのように。
まず第一に、中村家は羨む気持ちさえ失うほどのお金持ちであった。具体的な数字は分かりかねるが、小国の国家予算くらいではないかと噂されていた。父親は都内に立派な病院を営み、一人娘の理沙子を溺愛していたため、彼女は(少なくとも今世では)経済的なことに気を悩ますことはなかった。
また母親も、思わず口笛を吹きたくなるほどの美人であり、理沙子はその遺伝子をそのまま受け継いでいた。愛想と愛嬌を備え、とりわけ傾聴力に優れていたため、たいして面白くもない相手からでも、輝くものをいくつも持ち帰ってくることができた。彼女と話をしていると、まるで自分がとても面白い人間で、面白い人生を送っているような気になったものだ。
そんな調子なので、慢性的な鼻炎など誰も気にしなかったし、むしろ「その呪いを解かん」と挑戦するように、絶え間なく男たちが彼女に言い寄っていたくらいだ。かくいう私も、その列に並びたかったのだが、鼻息のあらい勇猛な漢たちの前では、私の存在など鼻紙のようなものだったのかもしれない。
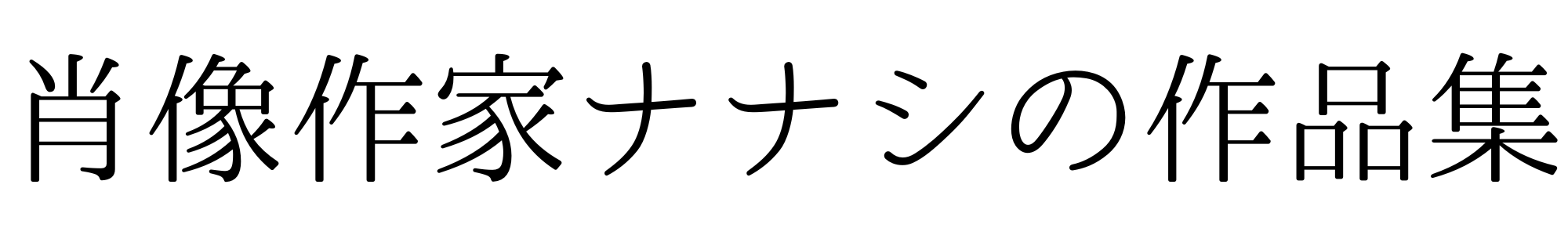
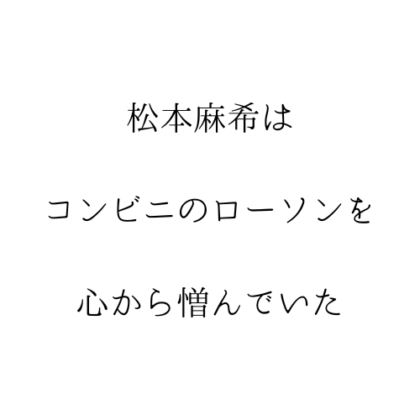
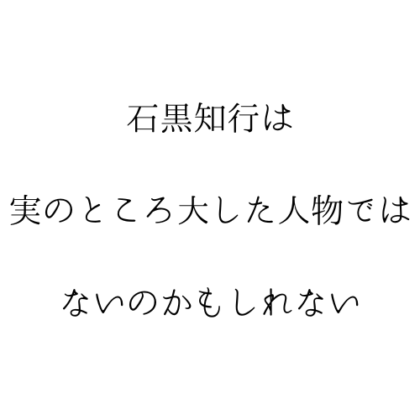
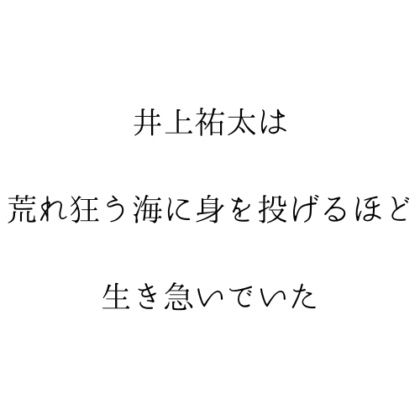
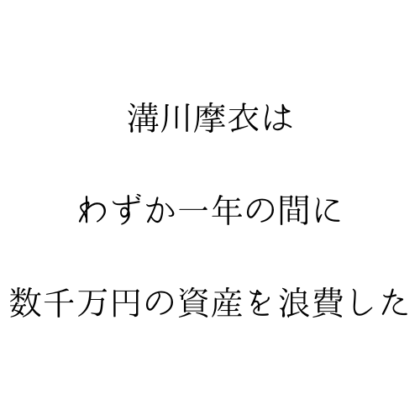

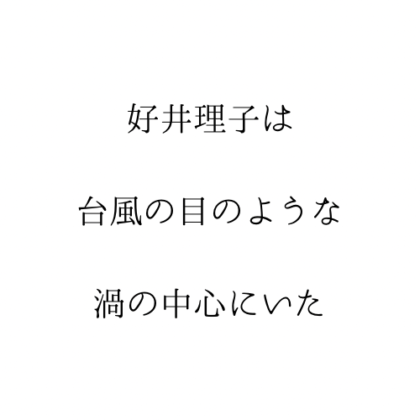
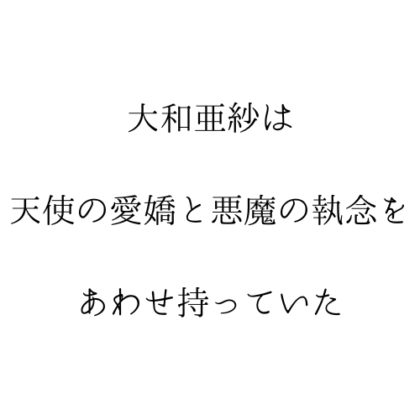
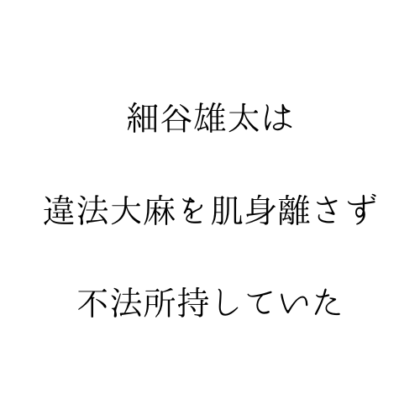
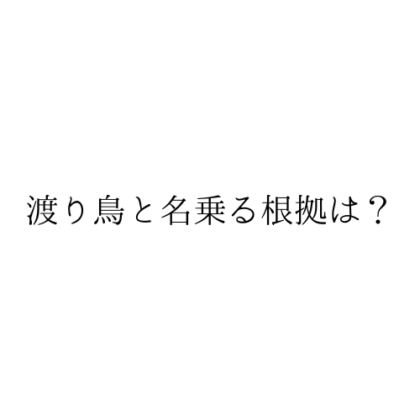

Leave a Reply