高瀬駿太は仮面を被った取締役だった
高瀬駿太は、鉄の仮面を被った無感情な取締役だった。
私が彼から受けた第一印象は、『付け入る隙のない鉄の彫刻』だった。30になりたての若者と聞いていたが、その眼光は東大寺の仏像のように鋭く、あご髭は庭園の芝のように整い、右手の薬指には指輪物語に登場しそうなリングが見られた。ひと目では何をしている人物なのか見当もつかず、ひと言では形容できない怪しささえ漂っていた。商売人にしては目つきが鋭すぎたし、弁護士にしては身なりが良すぎたし、医師にしては知性的すぎた。決して愛想は悪くないが表情は平坦で、まるで公式文書を直訳したような話し方をした。語句の選び方と文法は正確だが、そこから《感情》を読み取れないのだ。
駿太は、都会的な見た目の割に古風なところがあり、鍛錬を美徳としていた。もともと頭の回転が速く用心深い上に、規律と忍耐と反復によって、小細工が通用しない類の能力を身につけていたので、彼が何かで道を踏み外したり、致命的な失敗をすることはなかった。正の一次関数のように、ただ時間の経過に従って実績と信頼が積み重なった。気づけば取締役に就任し、アーク・ヒルズ・クラブに顧客を招き、宝石商や資本家から寵愛を受けるようになっていた。
私は駿太に対して、「この人に向かってあまりつまらないことは言えない」という雰囲気を感じていたので、しばらくの間、言葉を選んで話をしていた。持ち出す話題も、港区のビジネスマンが好みそうなものを選び、間違っても、今日のラッキーカラーや新作のコンビニスイーツの話はしなかった。しかし何度か顔を合わせるうちに、彼の中にいくつかの付け入る隙が存在することに気づいた。
たとえば駿太は、軽い冗談を話しても決まって笑顔を見せてくれたが、その表情はせんとくんのようにぎこちなく、笑い声も肺炎をこじらせた鹿の息継ぎみたいで説得力がなかった。また、酒を飲みながら一緒にスポーツ・チームを応援する場面でも、駿太の声援だけは、アザラシの鳴き声のように棒読みで迫力に欠けていた。彼が真剣に応援すればするほどチームが苦戦を強いられたので、途中から敵の側を応援させることにした。
要するに駿太は、理性にこそ一部の隙も無かったが、こと感情表現においては、幾分かの不器用さがみられ、それがとてもチャーミングな人物なのだ。だから彼の鉄仮面に騙されないでほしい。悪の手先だと思っていたけど実は味方だったスネイプ先生のように、仮面の下には温和で優しい青年が顔を覗かせるのだから。
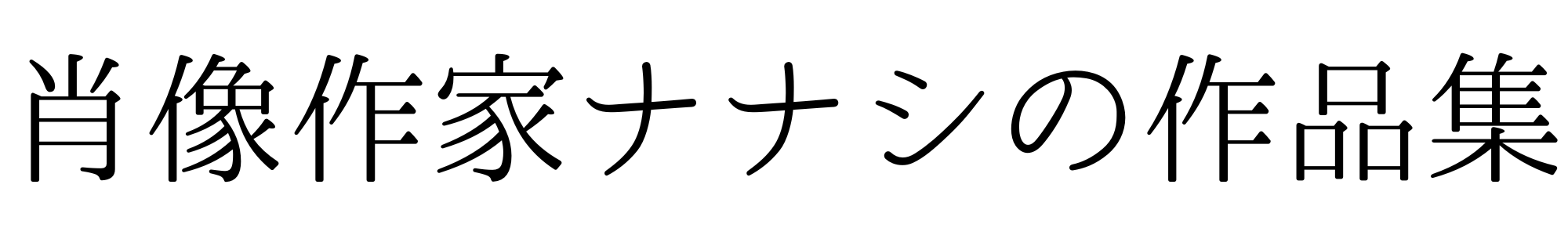
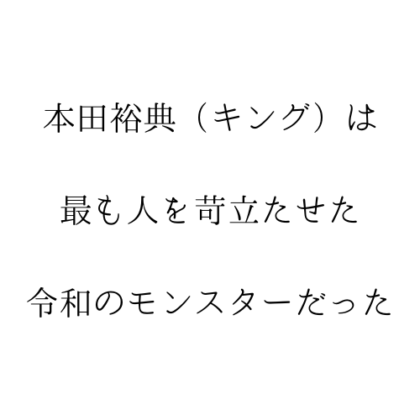
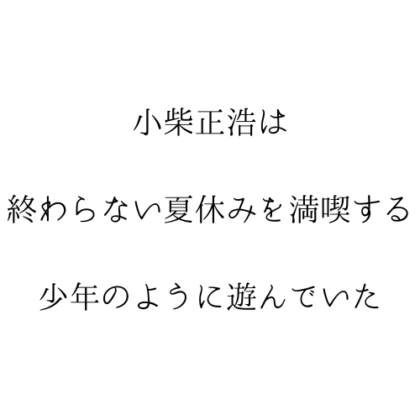
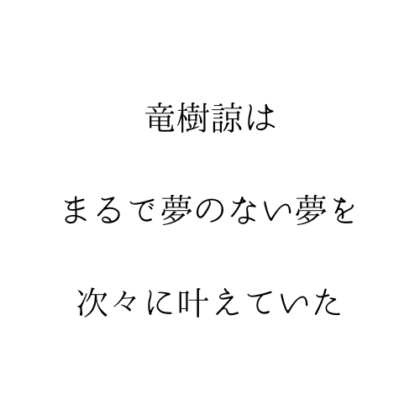
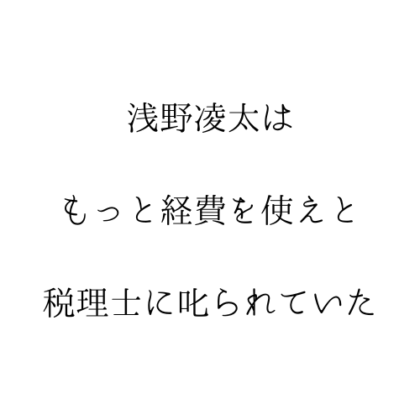
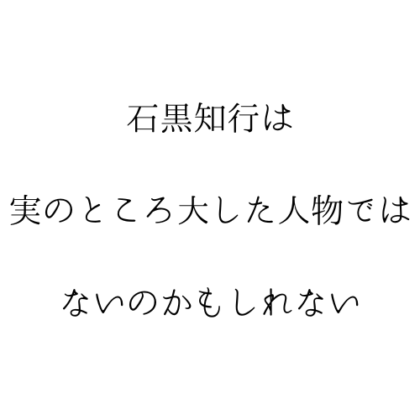
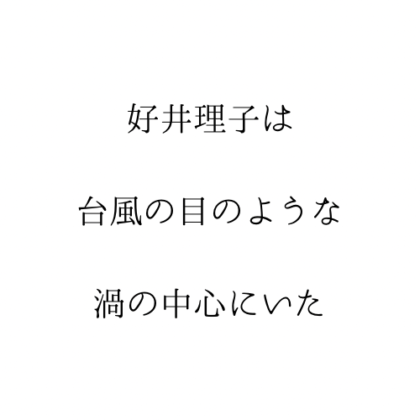
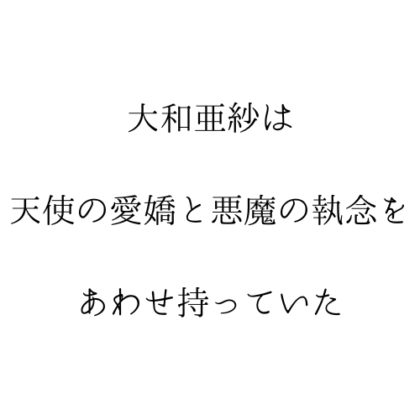
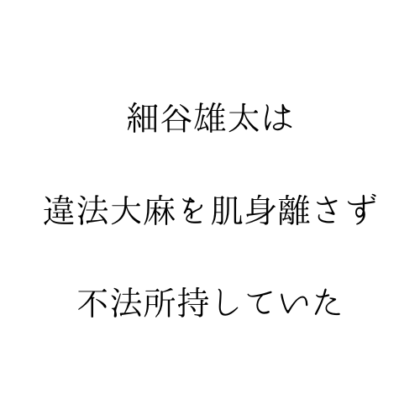
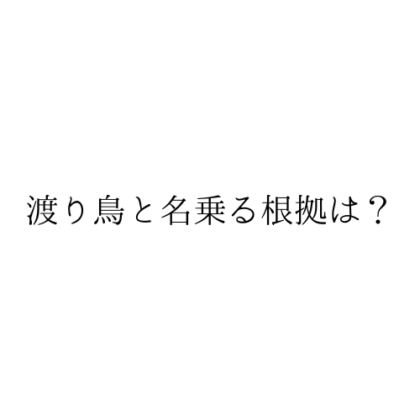

Leave a Reply