加藤唯はいつでも傘をさしていた
加藤唯は、いつでも傘をさしていた。
彼女は、雨男の父と雨女の母から生まれた純血の雨女であり、頭上にはいつも梅雨前線が広がっていたからだ。その資質は千年に一度の逸材とまで囁かれていた。
「加藤唯は雨を呼ぶ」というのは、彼女を知る者の間では揺るぎない定説であり、高い山に登れば気圧が下がるとか、海岸線を歩けば波の音が聞こえるといった、自然の摂理と同じものだと見なされていた。
そのため私も、彼女と会う時には必ず傘を持参しなければならなかった。本物の雨女の前では、ニュースの降水確率など、病床で聞かされる「みつをの言葉」くらいの慰めにしかならないのだから。
唯は、物心が付いた頃から雨の日が好きだった。とりわけ織姫と彦星が流す洒涙雨(さいるいう)を好んだが、月夜に訪れる月時雨(つきしぐれ)や、しとしとと降る甘雨(かんう)も、それぞれに等しく心を奪われた。好きな映画は「シェルブールの雨傘」で、好きな音楽は「雨に濡れても」だった。雨の日に飲むワインは格別だった。
そんな彼女には、幼い頃から不思議に思うことがあった。なぜ大人たちは、雨の日を「悪い天気」と呼ぶのだろうか。自分の目には天使からの贈り物に見えるのに、洗濯物が乾かないとか、前髪が癖毛になるとか、不満ばかり申し立てるのはなぜなのだろう。
歳を重ね、版画作家として確かな技術を身につけた唯は、幼少期から抱いていた疑問に一石を投じるため、ひとつの美しい傘を創った。その美しさは、母親がクラスの写真を見て、ため息をついて「この子はなんていう名前?綺麗な人ねぇ」という類の《言葉を超えた美》だった。
私が初めてその傘をみた時、シェルブールのギイが恋に落ちたように、一目で心を奪われた。何が何でも手に入れなければと彼女に連絡を入れた。幸いなことに傘はすぐに届けてもらえたが、不幸なことにその日からしばらくは晴れの予報だった。
私は一日でも早く傘をさしたかった(ささなければならなかった)ので、その日のうちに値の張るフレンチを予約し、とっておきのワインを餌に、半ば強引に彼女を街へ呼び出した。雲行きが変わり雨が降り出した。
雨の街で傘を開くと、まるでモーゼが海を割ったときのように、傘の内側の空間だけが安息の地に変わり、綺麗な色がさした。「傘をさすと色がさす」そう呟くと、私はひとりの人物の言葉を思い出していた。
Some people feel the rain. Others just get wet./Bob Marley
雨を感じられる人もいれば、ただ濡れるだけの人もいる
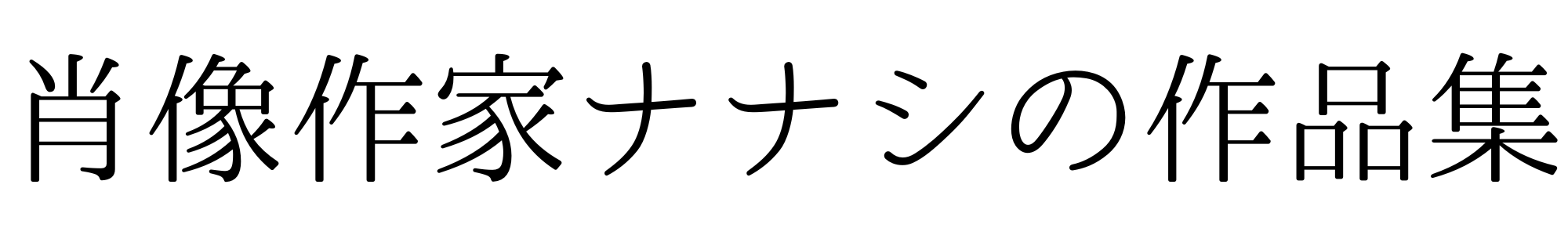
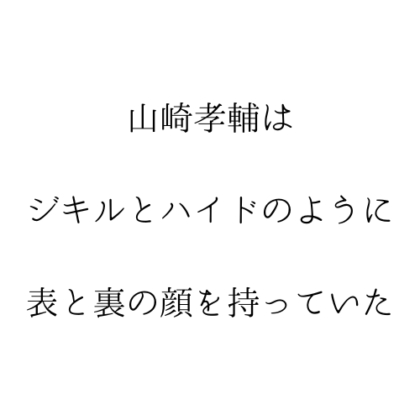
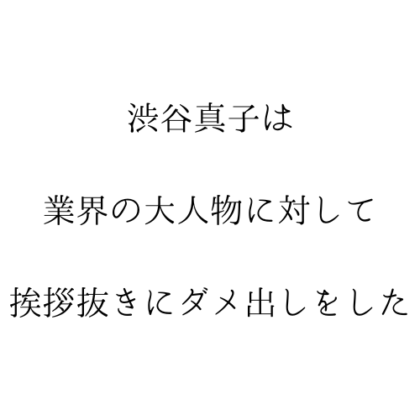
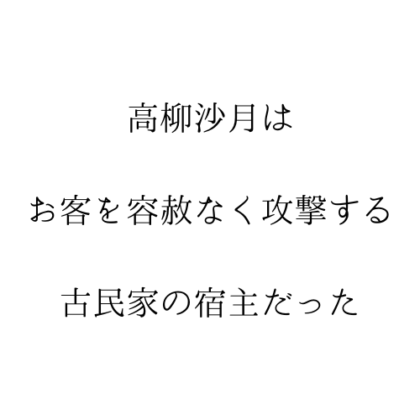
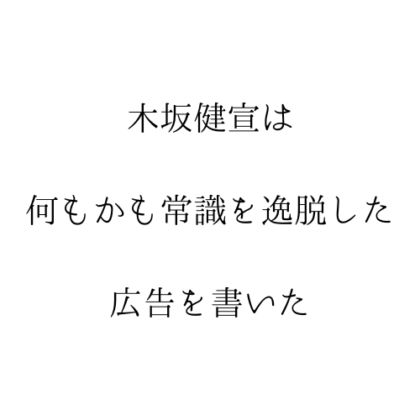

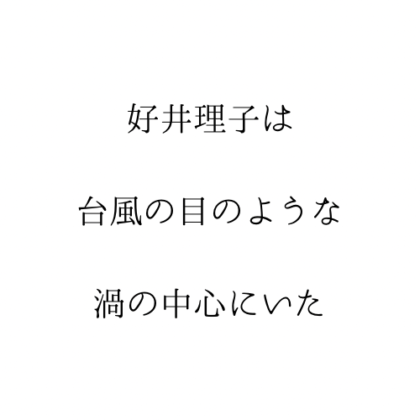
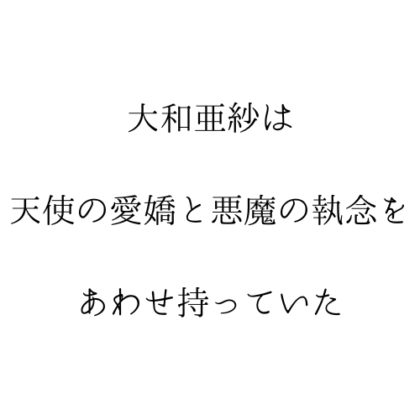
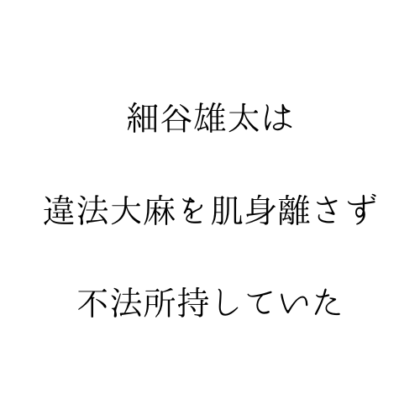
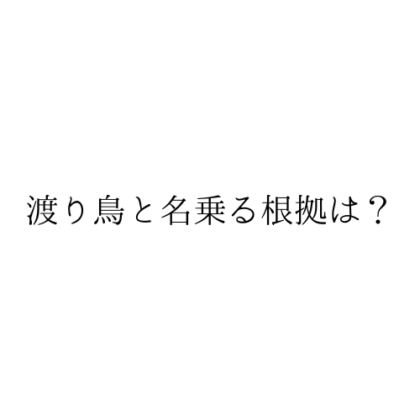

Leave a Reply