金澤祐樹は百を越える料理を生み出していた
金澤祐樹は、百種を越えるコース料理を生み出していた。
金澤の基本方針は、二度目に来訪するお客に対しては、前回と異なったお品書きを用意するというものだった。一日二組に限定しているのも、従業員を雇っていないのも、すべては金澤が自ら、客に合わせた細やかな対応をするためのものだった。医師がカルテを見て病状を絞り込むみたいに、金澤も予約表に目を通しては、一枚板の向こう側に座るお客の姿を想像して献立を考えた。組み合わせるお酒の提案や店内に流すジャズの選曲にさえ、そうした配慮を感じた。多くを語らない寡黙な性格ではあったが、私の顔を確かめると、貴方のことは覚えていますよという様子でこっくりと頷いたからだ。
金澤の料理を端的に表すなら《研ぎ澄まされた素朴》だった。引き算の料理と謂われる和食において、金に糸目をつけなければ、表現の幅は広がり間違いないものが提供できる。都内には三万や五万の価格帯の店が溢れているし、評価を得ている多くはそちら側だった。しかし金澤は高級食材に頼らなかった。むしろ純朴な食材を技で開花させるのが自分の仕事だと考えていたからだ。浅草の裏通り、目立たぬ場所に店を構え、広告や看板を出さなかったのも、料理とは関係のない経費を乗せたくないという考えだったのかもしれない。直ぐには繁盛しないかもしれない。けれどそのうちに解る人が見つけてくれれば良い。そんな時代に背中を向けるような人柄が、彼の料理にはよく現れていた。
彼の店が発掘されるのに多くの時間はかからなかった。金澤の料理に惚れ込んだある美術商の男が、「和食を知るならまずはここです」と言わんばかりに、海外の顧客を引き連れてくるようになったのだ。言うまでもなく、それは金澤にとって幸運の訪れだった。方針通り、男の来店に合わせて献立を考え、丁寧な仕事でもてなしをした。問題が生じたのは、来店回数が五十を超えたあたりだった。さすがの金澤も献立に頭を悩ませるようになったのだ。自信を持って出せる料理はひと通り提供した。ここから先は、やったことのない一皿を生み出し続けなければならない。金澤にとっては、使える言葉が一文字ずつ消えていく中で、連続小説を書き上げるようなものだった。しかしそんな心配をよそに、男はとびきりの食通を引き連れて、六十、七十、八十と来店し続けた。
来店頻度を考えると、そろそろ百五十回を超える頃だろう。鍛冶屋の折り返し鍛錬が刀の切れ味を良くするように、金澤の仕込む『炊き込みご飯』は、百五十の打ち込みを経て、至高の域に達しているかも知れない。
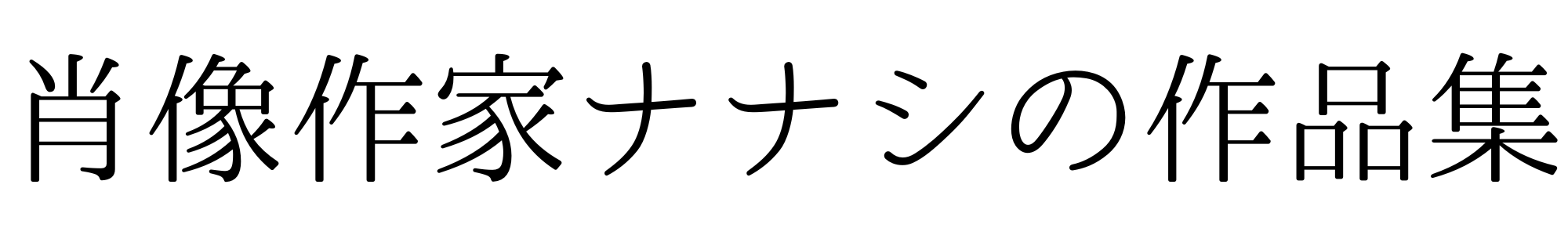
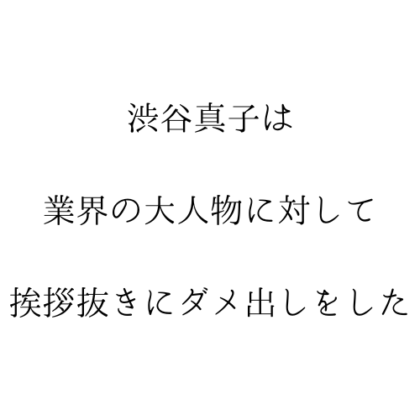
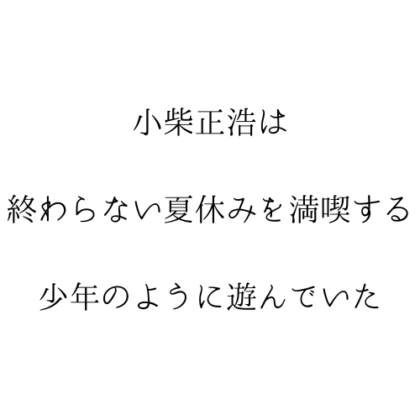
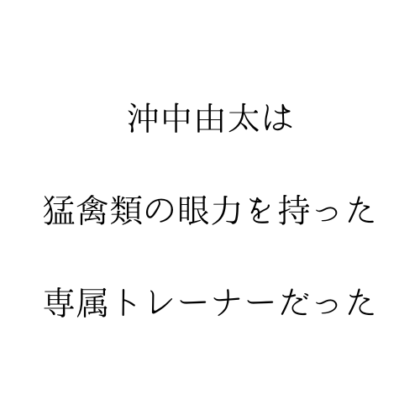
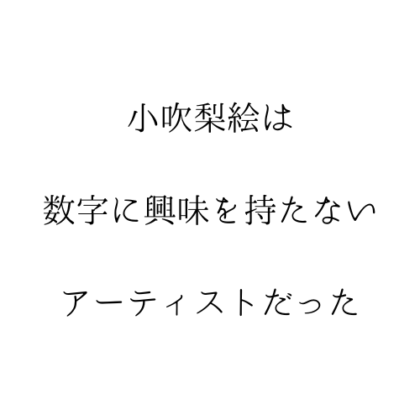
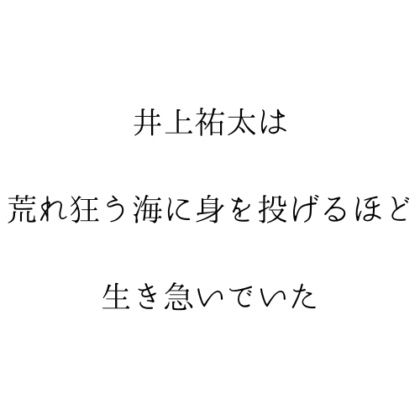
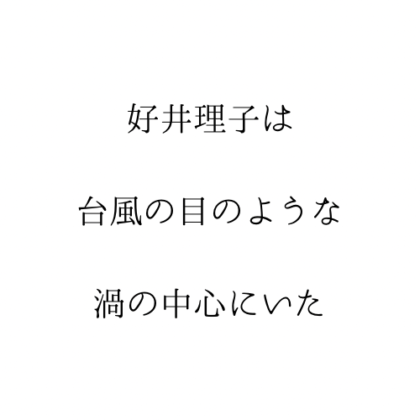
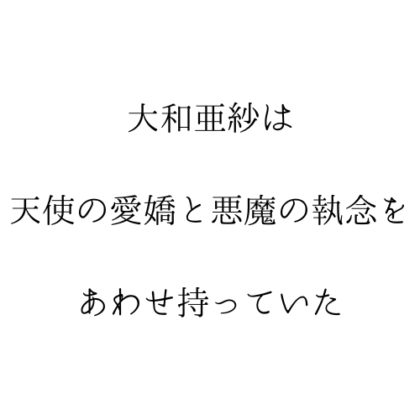
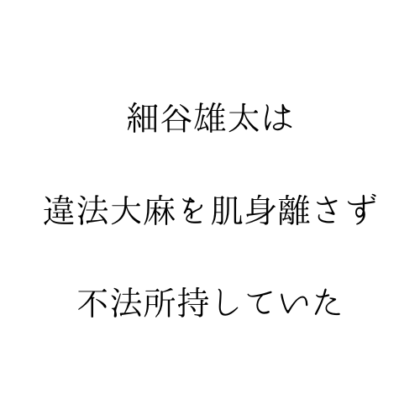
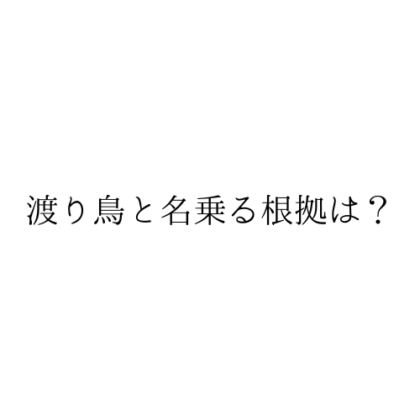

人の数だけ料理のレパートリーが存在するのですね。改めて、料理とは「おもてなし」に欠かせぬ物であると感じました。その国、土地に適した料理を味わうことで文化を学べる。そう言った意味で、本物の和食をこれまでは数えられるほど、いや一度もないのかもしれません。
日本の食卓から和食が消えぬよう、一度真剣に和食に向き合う必要がありそうです。