松﨑陸は失われた発明品を蘇らせていた
松﨑陸は、歴史から失われた発明を、ひそかに蘇らせていた。
京藍染師の松崎陸(Riku Matsuzaki)は、自然界のさまざまな植物から色素を抜き出し、それを用いて衣服を染めることで、植物の薬効成分を服用しようとしていた。彼は、国内随一の染色家の最後の弟子ということもあり、その志は純金のように清く気高いものだと評判だった。しかし、私が初めて彼の工房を訪れたとき、そこには嗅いだことのない匂いと、見たこともない姿の植物があり、おまけに陸の手は皮膚や爪まで真っ青に染まっていたので、私には森の悪い魔女が、怪しい薬草を混ぜて、いけない薬を作っている現場にしか見えなかった。
実際のところ陸は、表向きには《京藍染め》を専門にしていたが、人知れずにいくつもの植物を研究し、まるでバーテンダーが客の好みに合わせて酒をつくるように植物を調合していた。活発な男性には、汗の匂いを消し去る藍を用いてシャツや手ぬぐいを仕立て、生理に悩む女性には、体を温め血を清める紅花を用いて、はらまきや下着を染めた。飛鳥時代の冠位十二階に用いられた《十二色の色素》や、平安の法律:延喜式(えんぎしき)で定められた植物たちもくまなく理解していた。陸がその気になれば、あの頃の艶あるお肌を取り戻すシャツや、好きなあの人が私以外に興味を持たなくなる靴下だって作れるのかもしれない。
陸が染色家として目指すものは、正倉院に展示された紅花の布のように、たとえどれだけ手間暇をかけたとしても、1000年や2000年、色彩と薬効が損なわれない衣服を造ることだった。手軽に染まる化学染料があたりまえの時代に、そんなやり方は、ネット上はおろか、国立図書館にも情報がほとんどなかったので、骨董屋で古い巻物を買っては手がかりを探し求めた。その結果、彼は江戸時代の(おそろしく予算のかかる)農法で畑づくりを行い、室町時代の(おそろしく手間のかかる)手法で藍染めをした。質を追求しすぎるあまり、原価や人件費という概念をそっくり忘れていた。
陸は私よりも若かったが、彼の話は、齢80歳を超えた歴戦の猛者の武勇伝のように、新鮮な驚きに満ちていたので、私は彼の話をいつも心待ちにしていた。聴いたあとは、まるで自分まで一角の人物になったような気持ちにもなった。幸いなことに、陸には職人にありがちな頑固なところがなく、私が偉そうに友人に説明する姿を見ても、まるでタンポポを眺めるように微笑んで見てくれていた。彼の工房には、欧州や西洋からも噂を聞きつけた人が訪れるそうなので、陸の作品に原価や人件費が反映される前に、せめて衣服一式を揃えておかなければならない。
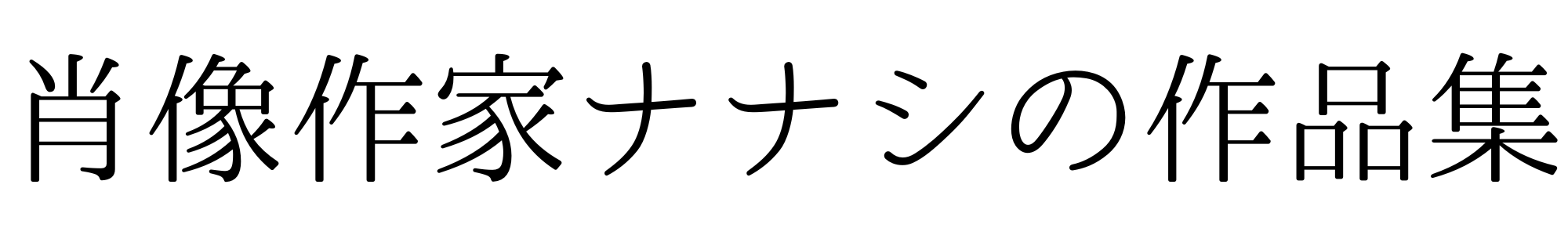
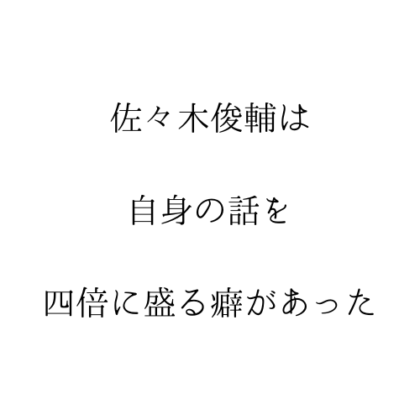
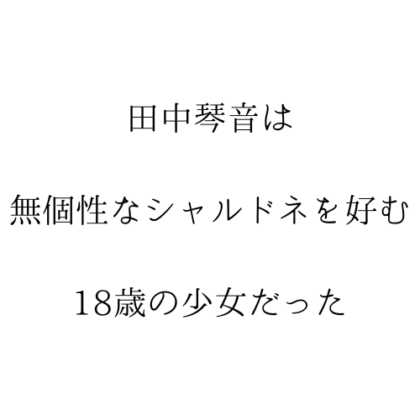
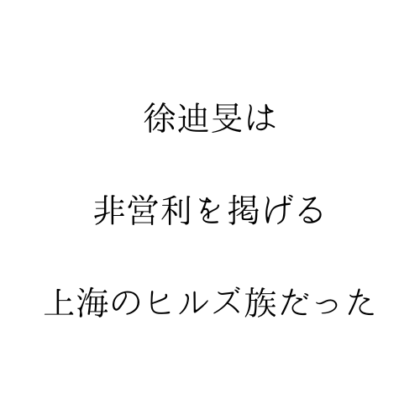
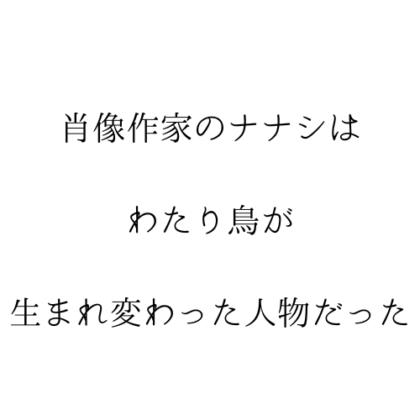
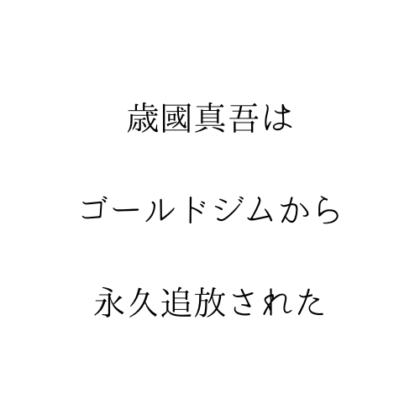
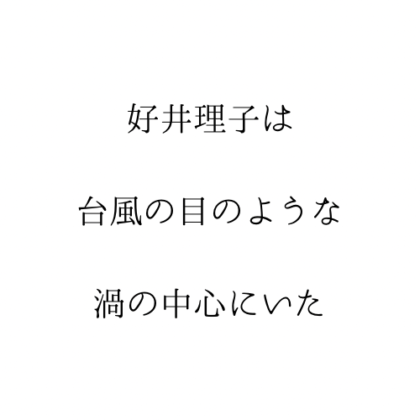
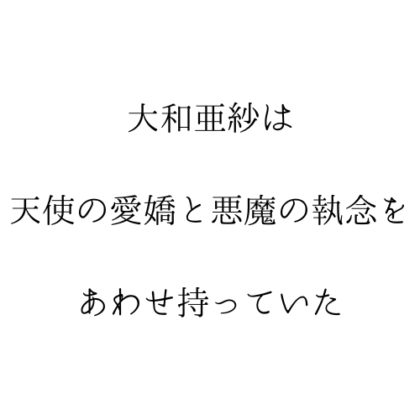
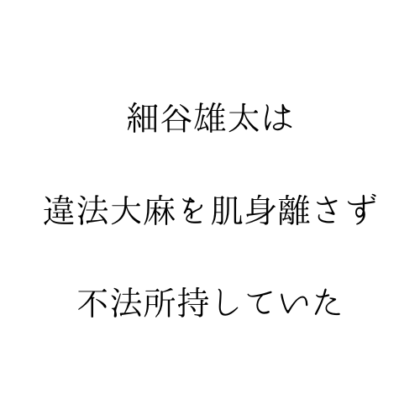
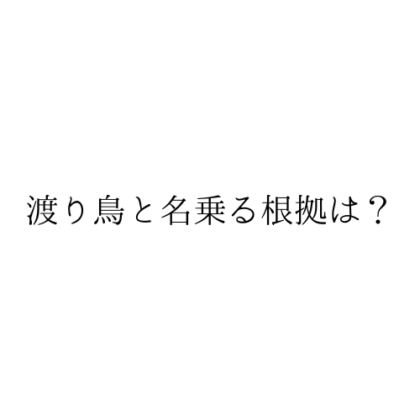

Leave a Reply