田中琴音はシャルドネを好む18歳の少女だった
田中琴音は、無個性なシャルドネを好む18歳の少女だった。
昔々…といっても数年前のことだが、私は夏の間だけ、とあるオーベルジュで勤めることになり、彼女はそこでの教育係だった。その店はグラス・ワインの種類が無計画に豊富で、常に「我々が飲むことを許された期限切れのワイン」が存在したため、愛好家の私たちはすぐに友達になった。
彼女は、法律上は酒が認められた年齢ではなかったが、ワインを自分専用グラスに注ぐ手付きが、お代官様が年貢を取り立てるときのように、あまりに無遠慮だったし、その嗜み方にも「この人に向かってはあまりつまらないことは言えない」という威厳があったので、(料理長を含めて)異論を唱える者はひとりもいなかった。
我々は勤務中でも、凛としたリースリングから、馬小屋を感じさせるシラーまで、あらゆる品種の葡萄を試したが、教育係はとりわけシャルドネの持つ『個性の無さ』に惹かれていた。それは単に「凡庸である」ということではなく、個性を主張する代わりに、自らが根を伸ばした土壌の魅力を伝える『描写力』に女性的な美学を感じたからだ。なるほど、奥ゆかしさとはこのことかと。
このように、18歳の少女にはとても大人びたところがあった。彼女は、目鼻立ちのはっきりとした美人で、餅つき名人のように手際が良く、誰に対しても公平で親切だった。だから職場の中でも常に一目置かれる存在だった。しかし彼女が同僚たちに無条件で好かれたのかというと、それは疑問だった。表立って彼女を悪く言う者はいなかったが、彼女には(私を除けばという話だが)友達と呼べるような人は一人もいなかったからだ。
思えば、彼女は他人に対して、クールで自覚的に過ぎたのだろう。彼女の中の大人にふさわしい要素と、まだ子供であり続けようとする要素が、上手く噛み合っていなかったのかもしれない。しかし私は、そうした外見の奥に潜んでいる温かく傷つきやすい何かを感じ取ることができた。それはかくれんぼをしている子どものように、奥の方に身を潜めながらも、いつかは誰かの目につくことを求めていた。そういうものの影を、彼女の言葉や表情の中に私はふと見いだすことがあった。
夏が終わると、我々のささやかな評論会も解散することになった。別れ際に彼女は、値の張るシャブリを贈ってくれた。そして2年後の夏、彼女は20歳という若さでこの世界から姿を消してしまった。またねも、じゃあねも、さよならもなく。
私は今でもシャブリを口にするたびに、余韻だけを残して去ってしまった彼女を思い出す。せめて天使たちがハープを奏でる庭園で再開した時に、彼女のためだけの美酒を選んでやれるよう、私は今も至高の一本を追い求めている。
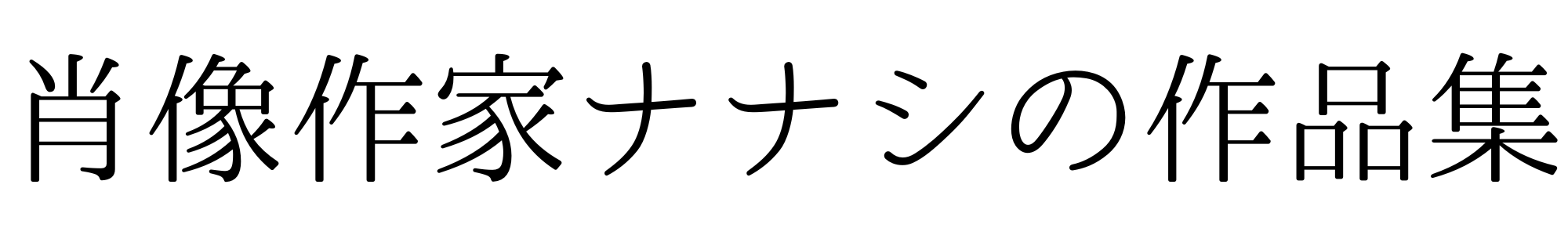
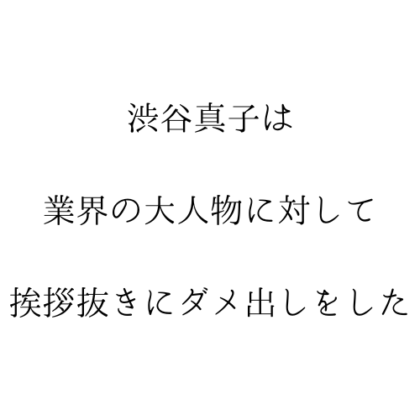
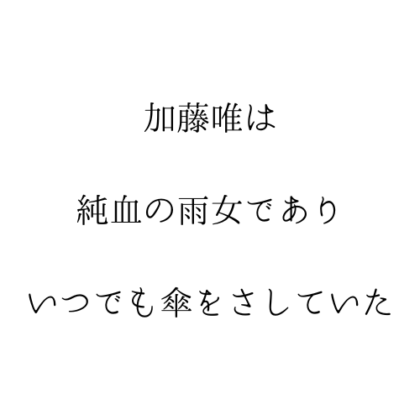
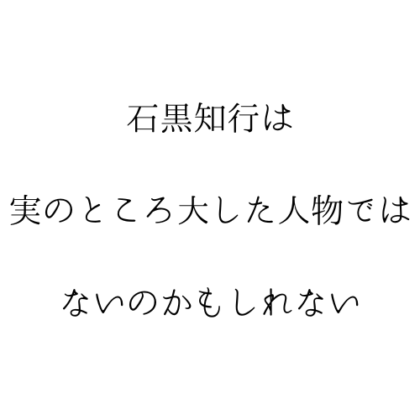
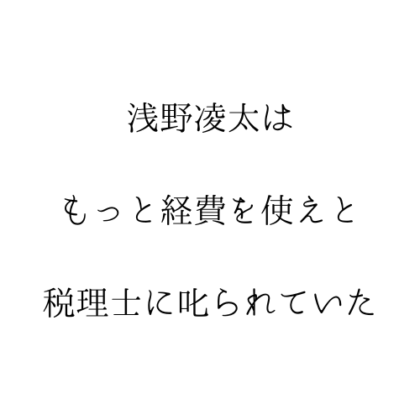


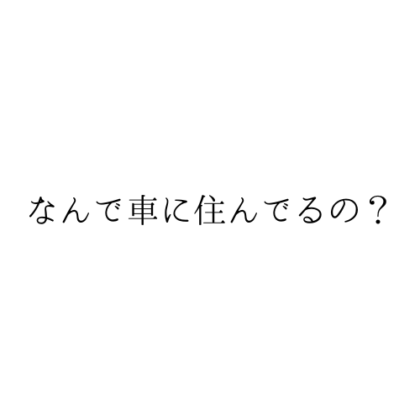
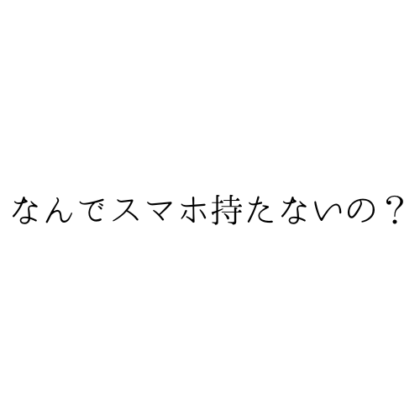
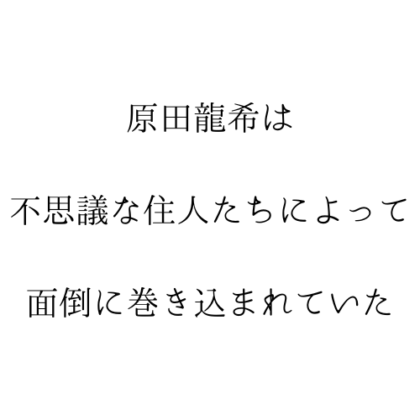
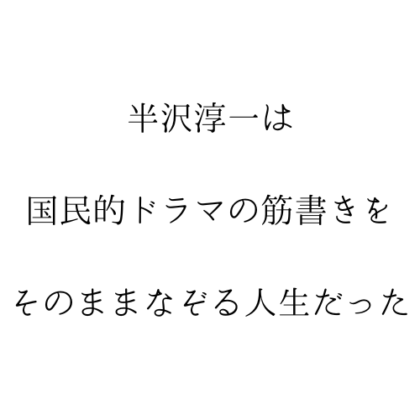
Leave a Reply