片野真一郎はやまびこ牛の下僕だった
片野真一郎は、35頭のやまびこ牛の忠実な下僕だった。
最初の牛を飼い始めたときから、片野の目には、群れる牛たちの面(つら)の区別がはっきりとついていた。同じ人間でさえ、遠く離れた国の民(たとえばタンザニアとナミビアとザンビア)を並べられては、みな一様に映るものだ。ましてや黒毛和牛を顔つきだけで見分けるというのは、ソムリエがワインの色調だけで何年物かを当てるような至難の業に思えた。しかも片野は、毛並みの色や角の年輪を題材にしても、うめことてるみの違いを明確に言い当てることができた。
さらに付け加えると、彼は見た目だけではなく、鳴き声にもはっきりと違いを見出すことができた。それは年頃の女子高生が「ヤバい」という言葉を文脈に応じてさまざまな用途で使い分けるように、牛が口にする「MOW(モゥ)」という単語の中に、「もう、触らないで」という《お叱りのMOW》から、「やだもう、この牧草美味しいわ」という《お悦びのMOW》まで、実にさまざまな音色の違いがあることを理解していたのだ。
そのような特殊な能力は、片野が牛飼いを生業にする上で、良い結果と悪い結果を同時にもたらした。良い点はなんと言っても、牛たちと親密になれたことだろう。アメリカン・エキスプレスの専属コンシェルジュが、担当顧客の嗜好に合わせて旅程を工面するように、片野もそれぞれの牛の体調や好みを把握し、細部まで行き届いたサービスを実現していた。
一方で悪いことも起きた。それは片野が牛の気持ちを理解しすぎてしまうあまり、彼らの無遠慮な要望まで一手に引き受けてしまったことだ。牛たちは何でも叶えてくれるサンタ・クロースの存在に甘え、より快適な寝床を要求し、より上質な食事を訴えた。片野は愛くるしい牛にせがまれると上手く断れなかったし、献身的で愛情深い性格も相まって、労働量が日に日に増え、寝る時間がなくなり、家計も圧迫されていった。
振り返ると30年あまり、片野は牛たちの従順な下僕となり、村から一歩も外に出ることを許されなくなっていた。独りの牛飼いとしては異例なことに、種付けから肥育、牛舎建設から牧草栽培に至るまで、牛にまつわる全てを担っていた。買い手の希望に合わせた畜産ではなく、牛の希望に合わせた畜産をしていたので、極端に出荷量が少なく、古くから付き合いのある顧客にしか回されなかった。
《幻のやまびこ牛》を育てる牛飼いの鑑(かがみ)は、食卓を囲んでこんな言葉を呟いていた。「命を奪って生きながらえているのだから、命の限りは尽くしたいのです。もちろん私のエゴですが。」
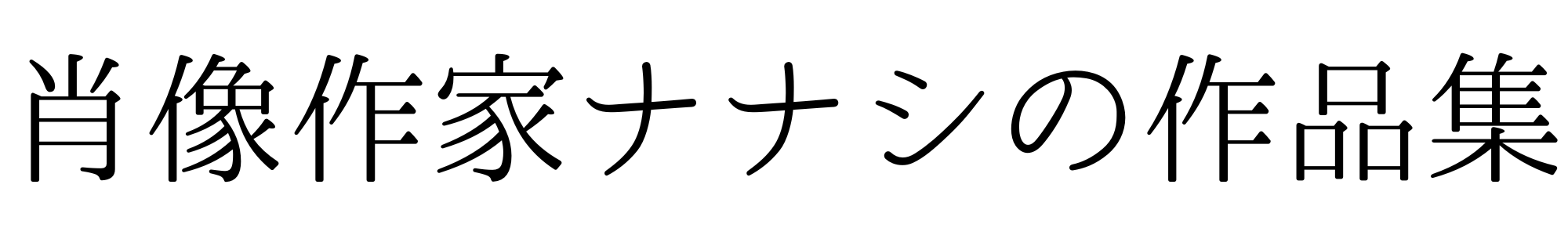
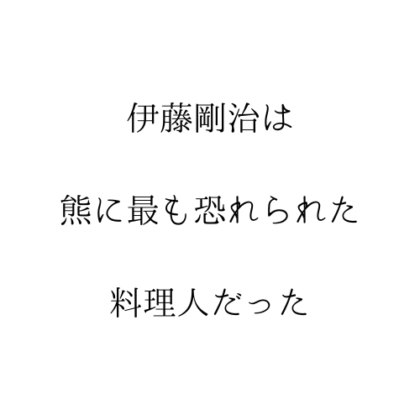
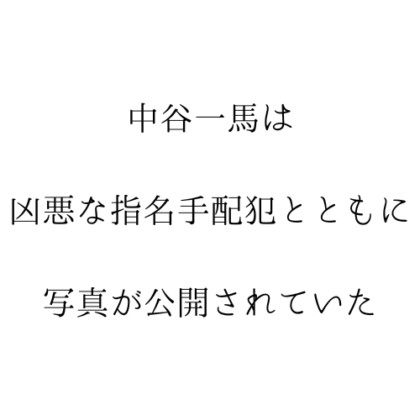
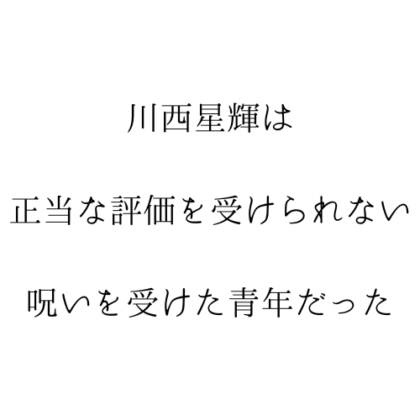
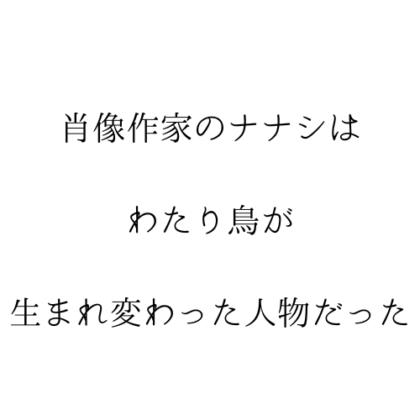
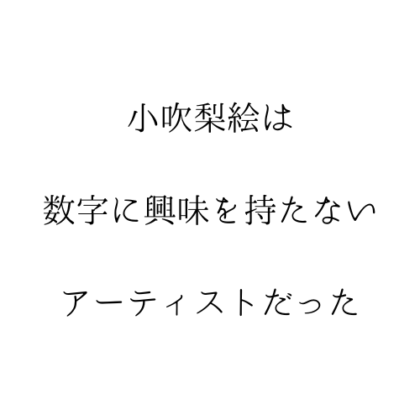
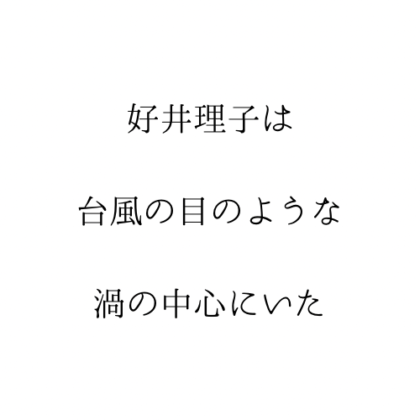
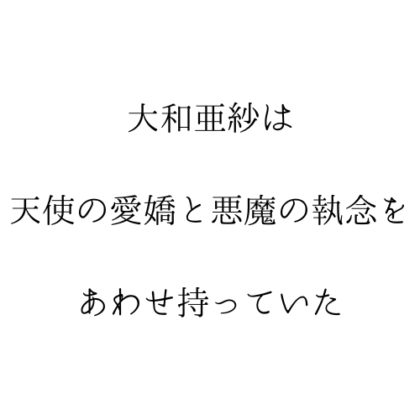
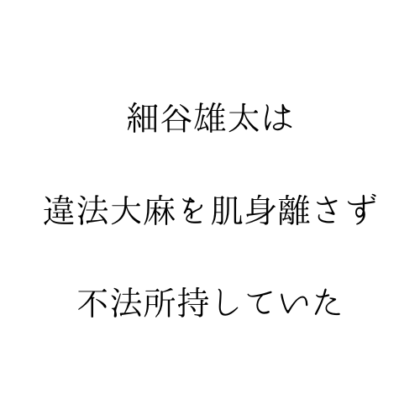
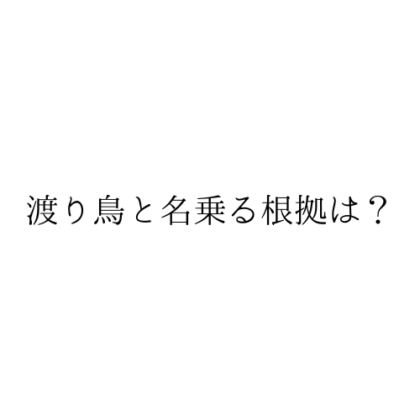

Leave a Reply