髙山正史は神戸で最もワインを開けていた
髙山正史は、神戸で年間に消費される半数のワインを開けていた。
美食家の髙山は、フランスの葡萄農家が一目を置くほど、ワインを消費する人物だった。週に7日、年間365日、熱心なイスラム教徒がアッラーへの祈りを欠かさぬように、髙山も肝臓を休めることなくコルクを抜栓した。彼は量を飲むことで有名だったが、宝探しに成功した海賊船の船長がやるように、高価な酒を仲間たちに惜しみなく振る舞うことでも評判だった。この街で消費されるワインのうち、少なくとも半数は髙山が関係していると噂されるほどだった。彼がこれまでに納めた金額は、(直接的に)いくつもの飲食店の経営を支えていたし、(酒税として間接的に)神戸市民の暮らしを豊かにしていた。私が初めて彼と出逢ったのも、やはりワインの品揃えに定評のある北野の割烹料理屋だった。
カウンターに座る髙山は、店主に向かって、次は2014年のラ・ターシュを開けるようにと言った。既に料理は終盤で、何本か飲み終えた痕跡もあったが、彼は「ここからが本当のお楽しみの始まりだ」という様子だった。浅識の私でさえ、ロマネコンティ社の葡萄酒が、単なる飲み物ではなく、芸術品や有形資産に属するものであることは知っていたので、コルクを抜く音に合わせて小さな拍手を送ってみることにした。髙山は私の姿を確認すると、懐かれてしまった野良猫に食事を分け与えるみたいに、「一杯どうですか」とグラス・ワインを振る舞ってくれた。初めて飲むラ・ターシュは、今夜死んでも文句は言えないなという味だった。私が感激のあまり小躍りをしていると、髙山は「ワイン好きはくまなく私の友達です」という表情を浮かべ、「今度、家に飲みに来てください」と連絡先を渡してくれた。そうして私はワインをご馳走になった上に、無遠慮かつ厚かましくも、彼の家に遊びに行くことにした。
言うまでもなく、髙山邸の家飲みは何から何まで格別だった。乾杯のドン・ペリニヨンから始まり、コルトン・シャルルマーニュ、エシェゾーにミュジニー、ラトゥールからマルゴーまで、まるで明治の鹿鳴館みたいに次から次へと美酒が振舞われた。お代わりは求めるだけ注ぎ足されたし、お抱えの料理人が、鰹の藁焼きから雲丹の手巻きまで、合うつまみも用意してくれた。私はとうもろこし詰め放題サービスで袋が破れるまで押し込む主夫のように、飲めるだけ飲んだ。西の貴族の晩餐を体験した東の庶民として、言える重要なことがひとつある。
いいお酒はどれだけ飲んでも、翌日に持ち越さない。
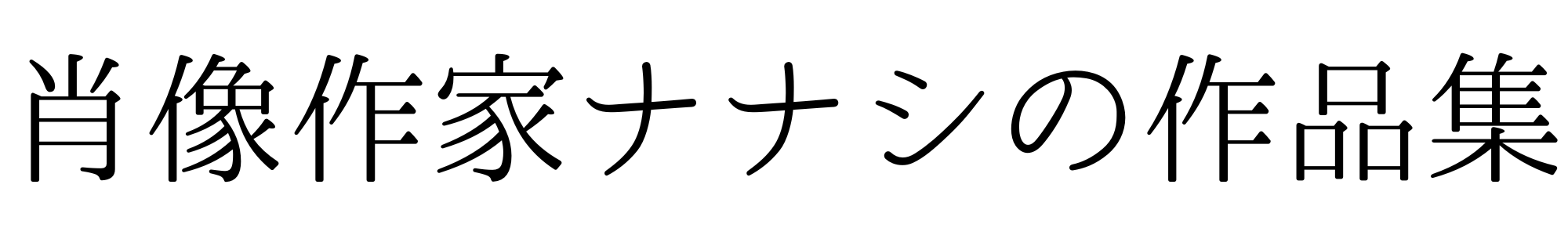
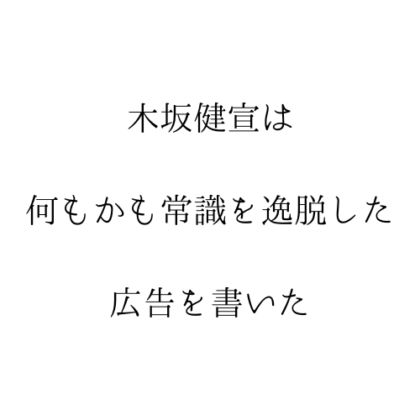
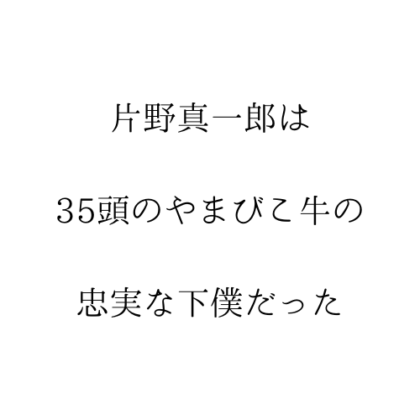



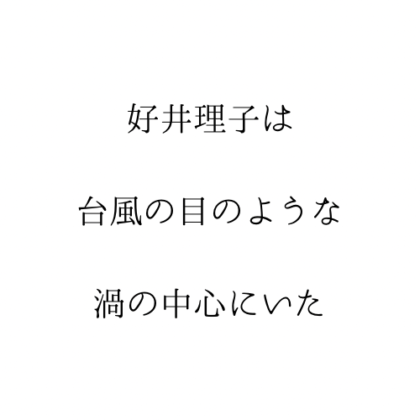
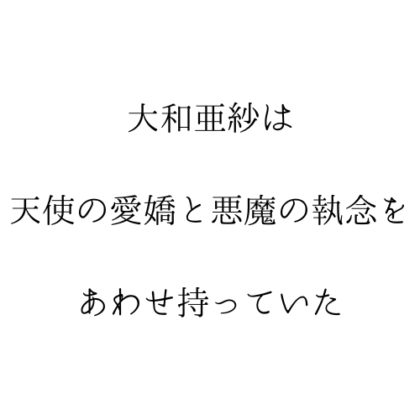
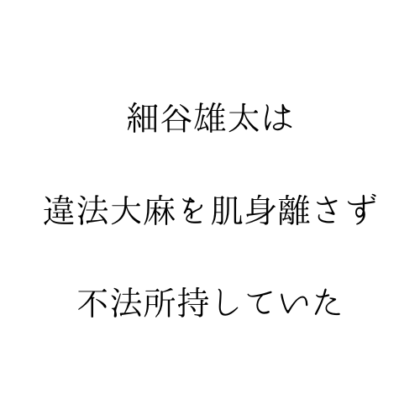
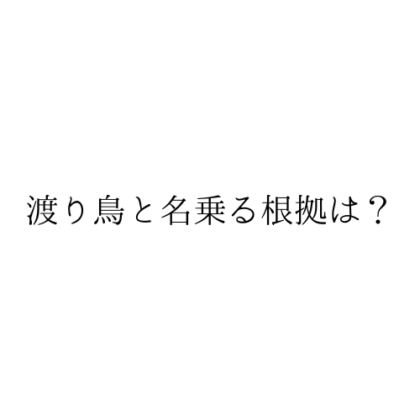

Leave a Reply