手塚孝幸はマクドナルドと酒に溺れた
手塚孝幸は、背徳感を感じつつもマクドナルドと酒に溺れた。
久しぶりに会った孝幸は、七日後に殺される呪いのビデオでも見たかのように、無気力で放心していた。問いかけへの反応は鈍く、聞き逃しもあり、返答の内容も的を得ないものだった。彼には天真爛漫で行動の読めない妻がいたので、いよいよ彼女が何かやらかしたのかもしれない。たとえば、一家の財産をスクラッチ・ジャンボにオール・インしたとか、地震のニュースをみて、赤十字基金に大量誤送金をしたとか、そういう類の厄災が降りかかったのかもしれない。
しかし事情を訊いてみると、死の宣告はおろか、妻の暴走も今のところは起きていないらしい。むしろ、生活の状況はすこぶる良くなっていた。孝幸は、業務の効率化を追求し続けた結果、30代の半ばにして、もうほとんど仕事をしなくても暮らしていける状況を実現していた。その生活は、若い頃の彼が夢見続けてきたものだった。それなのに今、心の内にあるものは、何もやるべきことがないという退屈さと、やりたいことがないという虚無感だった。夢遊病患者のように夢と現実の区別が付かず、ただ時間を浪費するだけの怠惰で自堕落な生活を送っていた。孝幸はそんな非生産的な自分に嫌悪を感じながらも、具体的な解決策が見えないことに酷く傷付いていた。
なるほどそれは深刻だ。私は精神病棟の主治医がやるように、どのくらい駄目になっているのかを詳しく尋ねることにした。悪夢障害や自殺念慮がみられるなら、通院が必要かもしれない。しかし、孝幸の口から語られたのは、「読書をしようとしても読むことができない」とか、「運動をしようとしても動く気にならない」など、ダメ人間コンテストでは初戦も通過できなさそうな取るに足らない悩みだった。おまけに医療保険だって効かない。そこで私は、「やることが中途半端だ、堕ちるときは地の底まで堕ちるべし」と、百通りほどある処方の中から特に優れているものをひとつ授けた。
翌日、孝幸は最寄りのマクドナルドへ向かい、ダブル・チーズ・バーガーを三つに、ラージ・サイズのポテトを二つ、チキン・ナゲットを三箱持ち帰り、マグナム・サイズの赤ワインを豪快に開けた。モニターに映した都市伝説の動画を横目に、スマホでパズル・ゲームをしながら、胃腸に負担をかけるであろうこのご馳走たちを欲望のままに貪り始めた。このような食事は、もう何年も摂っていなかったので、理性では背徳感を感じつつも、本能が歓んでいることは認めざるを得なかった。次第に、霜焼けになった手が流れる血液で温められるように、身体と心が《緩んだ》という感覚を確かに感じることができた。これこそが、かの有名なマクドナルド療法である。
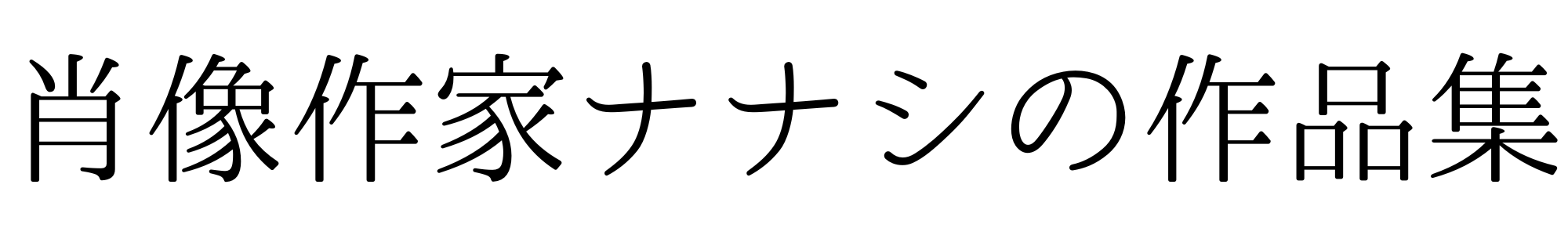
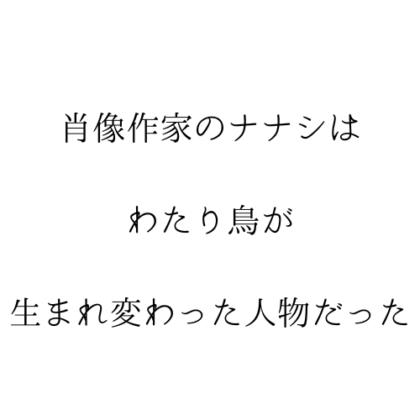
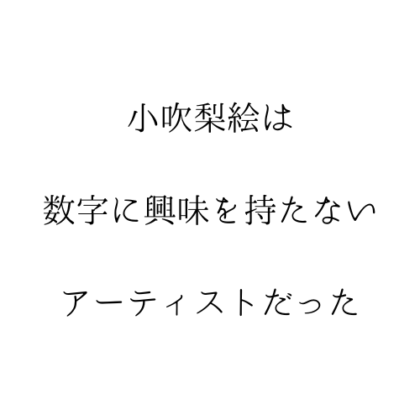

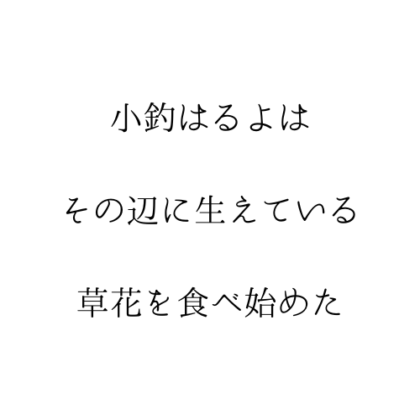
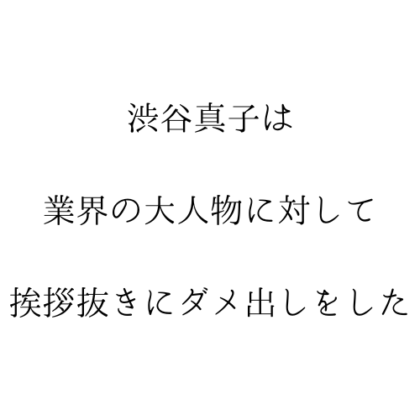

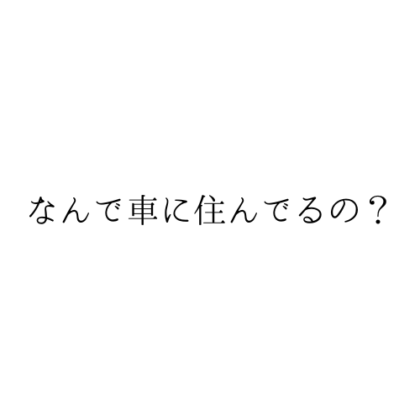
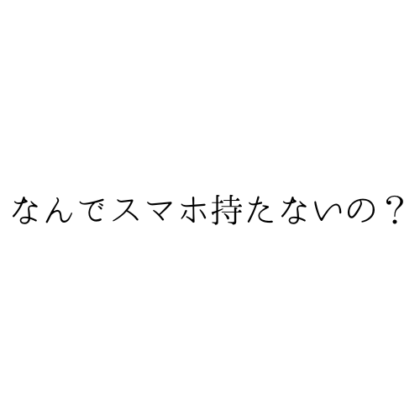
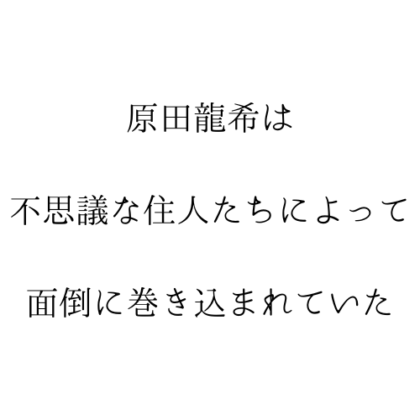
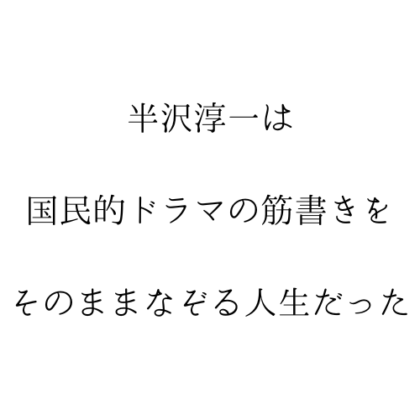
Leave a Reply