小釣はるよはその辺の草花を食べ始めた
小釣はるよは、その辺に生えている草花を食べ始めた。
備長炭への火おこしが終わり、さぁいよいよ肉を焼こうとしたそのとき、小釣はその辺に生えている野草を適当に摘んで、肉の隣で焼き始めた。犠牲になった尊い黒毛和牛に感謝のお祈りでも始めるのだろうか。伊勢生まれと聞いてはいたが、古神道の教えにはそういうものがあるのだろうか。そう思いながら彼女の動向に注目していると、私の予想に大きく反し、小釣はまるでサムギョプサルでも食べるかのように、野草で肉を包み上品に口へ運んだ。その味に納得がいったのか、嬉しそうな表情と軽やかな足取りで、あちらこちらで野草を集めだした。これは今食べる分、こっちはお風呂に入れる分、そして残りは肌に塗る分。そのような調子で草をグループ分けし、有り難そうに持ち帰ろうとしていた。
ひとつまみの野草を入れた水を飲む小釣を見て、私は彼女のお腹を心配した。ばい菌がいっぱいいるんだから、せめて消毒した方がいいんじゃないかと。しかし彼女は、私が飲むミネラル・ウォーターを見て、逆に私のお腹を心配していた。貴方が飲んでいるのはもう枯れてしまった水。野草たちに蘇らせてもらった方がいいんじゃないかしら、と。たしかに私の胃腸は発情期のリスみたいに繊細だが、だからといって見ず知らずの女性が勧める生の野草を口にするなんて、今どき野良猫でもしない。すると小釣は、「それなら火を通すからお味見してみて」と、《香ばし焼き野草、厳選十二種のハーモニー》を私の皿に乗せた。僕は山羊でも鹿でもないんだぞ、と文句を言いたくなったが、小釣はその会場にいた誰よりも肌艶がよく、健康的な美しさがあったので、説得されるがまま食べてみることにした。はじめて食べた春の草は、葉物の野菜を食べるのと変わりはなく、ほのかに森の香りが鼻から抜けた。
縄文の人々が、木の実や草花に命を繋いでもらったように、小釣は野草の持つ力を誰よりも信じていた。農薬も肥料も使わず、自然が育てた《いきものの糧》を人が美味しく食べる術も熟知していた。独りで始めたことだったが、次第に彼女の思想に共感する者が増え、いつしか大学や企業も協力するようになっていた。膨大な知識もさることながら、彼女は草花から意志を受け取ることができたので、自然の方から差し出してくれる恵みを、自然のままに享受していた。野草を摘む小釣を見ているとこう思う。この世界は宝物で満ちているんだと。
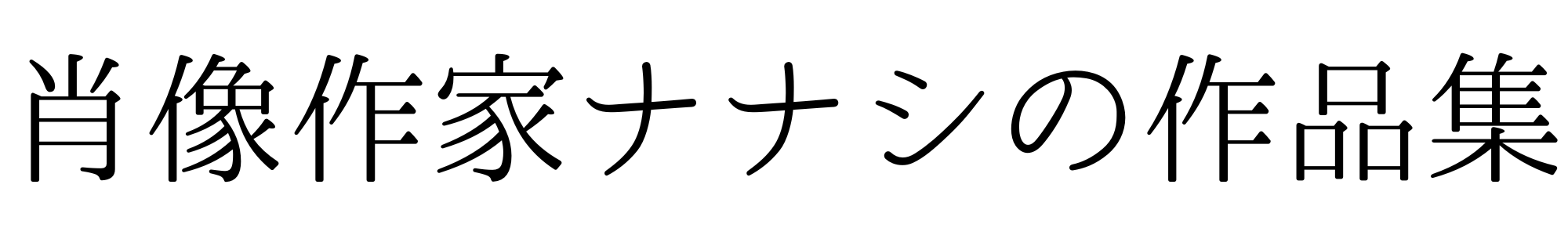
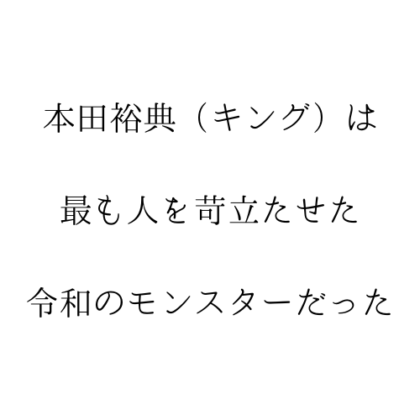
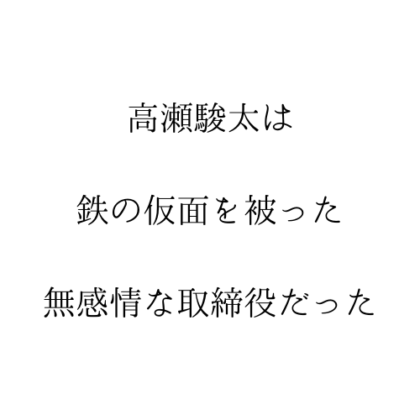
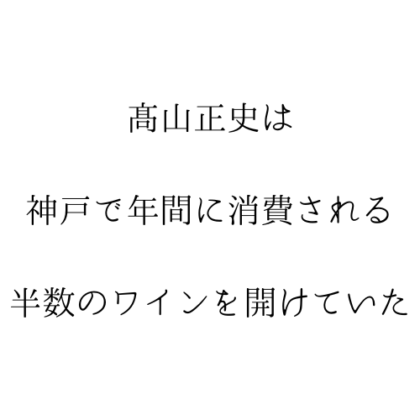
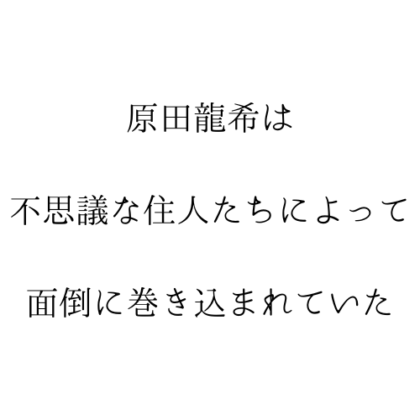
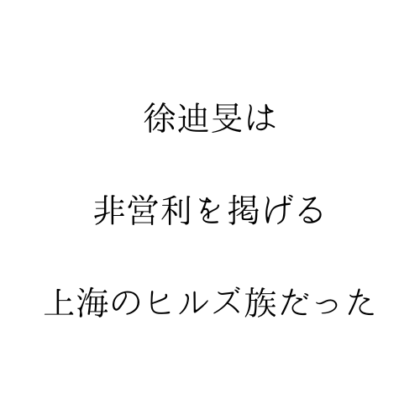
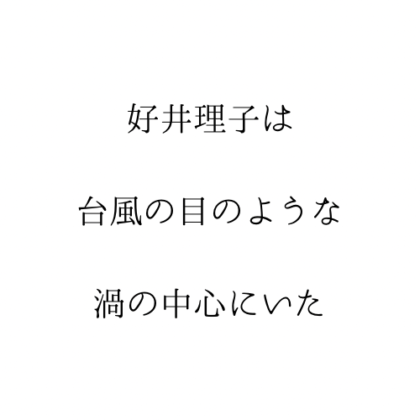
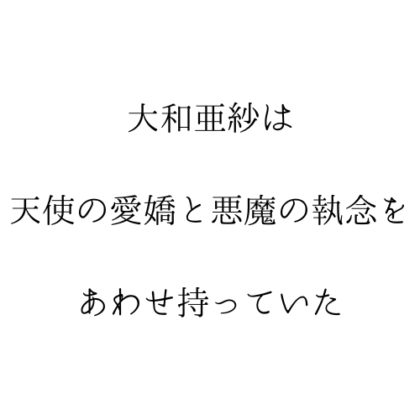
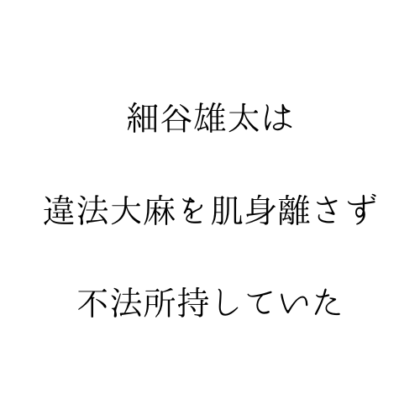
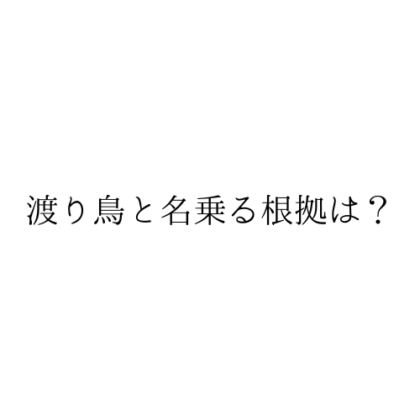

幼少時代に山を駆けずり回って、野草を採ったり、木の実を採ったりしていたことを思い出しました。まさに山の宝庫。数分でそのような所へ行ける環境であったことに今では感謝するばかりです。そのように育った私は、食べられる野草、花を見つけると手を出し、いつものように花の蜜を吸っていたら、姉に「そこ、犬の散歩コースだよ」と言われ、それからは場所を選ぶように。少なからず、枯れたミネラル・ウォーターよりは栄養があったかもしれませんけどね。