渋谷真子は業界の大人物にダメ出しをした
渋谷真子は、業界の大人物に対して、挨拶抜きにダメ出しをした。
これは彼女がひとりの狩猟者(羆撃ち)として、生命と真摯に向き合ってきたからかもしれないが、真子はどのような人物に対しても、忖度をしたり、媚びへつらうことがなかった。それこそ国を代表する経営者やノーベル医学賞受賞者、あるいは押しの強いアンミカを前にしたときにも、まるで山猫や山犬に語りかけるときのように、ごく自然な調子で接することができた。諸外国の要人を相手にしたときも、ため口やお腹つんつんを躊躇わずにやってのけたので、周りも者は肝を冷やすことになったが、彼女はただ無邪気な笑顔を浮かべるだけだった。そのうち等しく死ぬんだから偉いも偉くないもないじゃない、と言わんばかりに。
真子は、目の前にいる一個体の生身の人間と、そこに被せられた社会的な冠を、まったく別の領域に属するものとして区分する能力があった。だから、どれだけ立派な肩書きや高価な所有物を並べたところで、彼女の評価軸には何の影響も与えなかった。よろしい、あなたが社会的に立場があると言いたいことはわかった。でもあなたという人物を知るうえで、付属物の情報はかえって邪魔になるだけなので、一旦横に置いておきましょうよ。もう少し親密な関係になったら、お酒の席で聞かせてもらおうかしら、と。そんな調子で真子は、相手が著名人であるほど、あたかも大したことではないかのような態度をとり、逆に相手が社会的弱者だと名乗れば、軽んじずにその者から宝物を探し出そうと心がけていた。
私が初めて彼女と会ったのは、ペナン島に出張で出かけているときだった。当時の私は人生における幸運が重なり、仕事も遊びも肌艶も絶好調で、今期もっともノリに乗っている人物のひとりだった。繋いでくれた女性は、私のことをまるで一角の大人物のように丁寧に紹介してくれたが、真子は「そんな前置きは一言も聞いていなかった」という様子で、さも興味なさげな挨拶をした。最初から友達口調で、ビールを飲みながら話し、髪の色が服に合っていないだとか、眉毛の角度に品格がないだとか、のっけから一通りのダメ出しをくらった。おまけに彼女は金色の髪にこんがりと焼けた肌をしていたので、「なんて失礼なギャルなんだ」と物申したくなったが、その指摘は意外にも的を得ていたし、聞いておいて損はないと思える説得力があった。会話を続けるうちに、我々の間には色々と共通する部分があることもわかり、最終的には仲良しになった。
今や真子自身が、外交の窓口となり、聖火ランナーを務め、高級スポーツカーを乗り回すようになったが、そんなことは彼女の人間的魅力を知るうえで、なにひとつ参考にしてはならない。
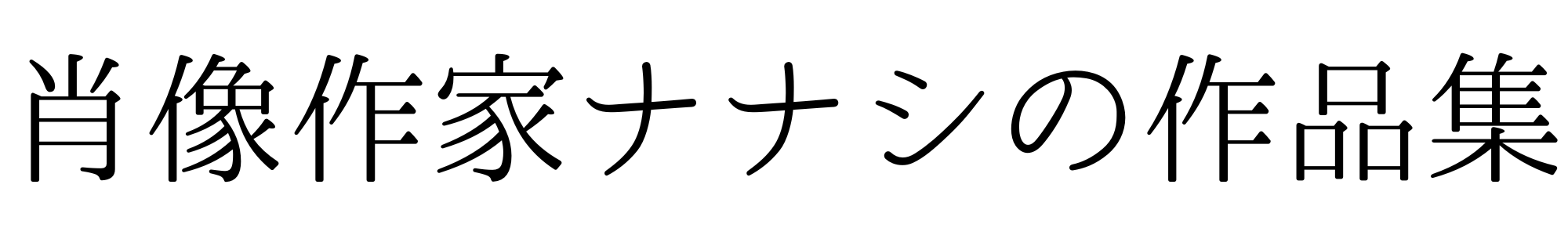
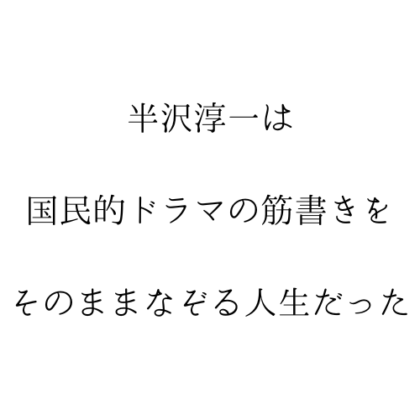
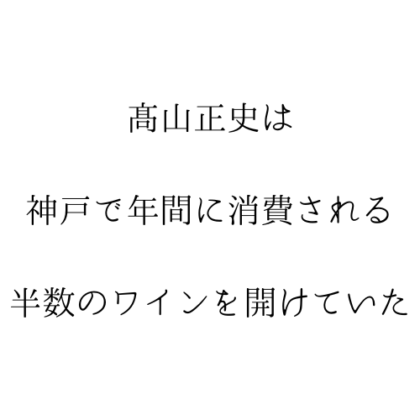
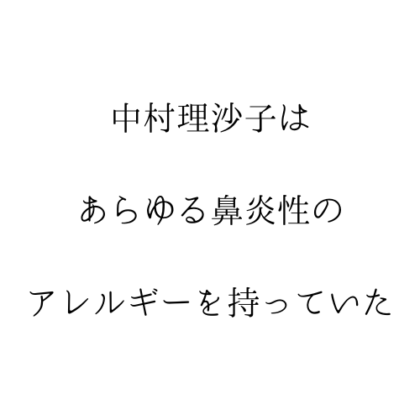
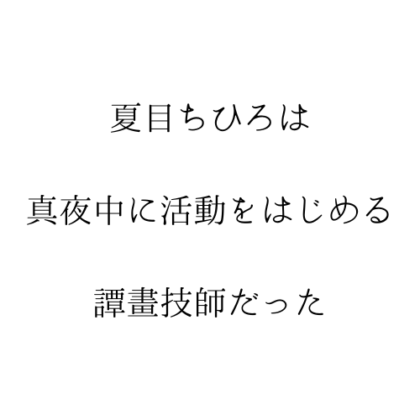
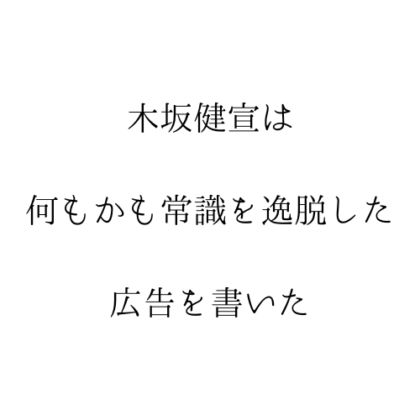
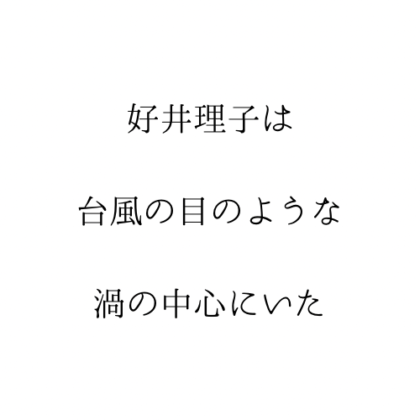
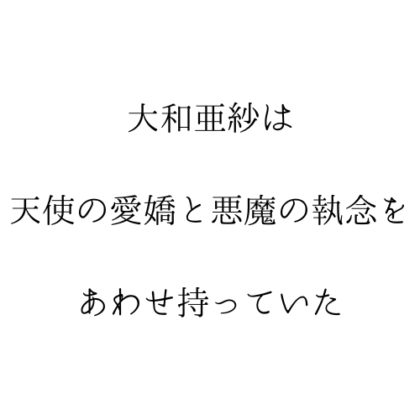
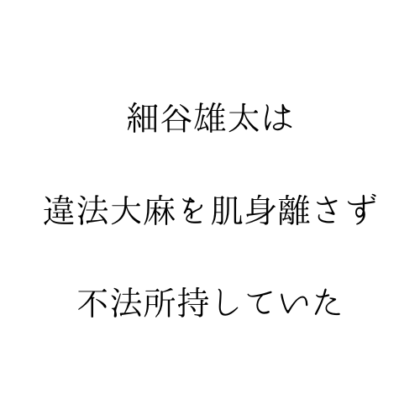
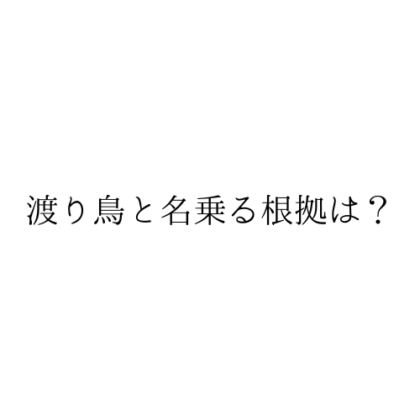

Leave a Reply