好井理子は台風の目のような渦中にいた
好井理子は、台風の目のような渦の中心にいた。
彼女の一族は神事に携わり、聖地を守りつづけてきた。親兄弟に親戚、祖父母にその先祖と、血縁関係を地平線まで見渡すかぎり、みな天に仕えることを生業としていた。だから高校を卒業した理子が、彼らと同じ道に歩みを進めたのは、年頃のカンガルーがボクシングを始めるのと同じくらい自然なことだった。そこに一切の迷いはなく、「もしも」や「しかし」、「あるいは」や「けれども」が入り込む余地もなかった。
理子の生活態度は、天国行きの推薦枠を約束された優等生のようだった。十歳になるまでには、雅楽や茶道を身につけ、一日も欠かすことなく美しい所作で祈りの歌を届けていた。季節や曜日に関わらず、朝五時には御勤めを始めていたし、いつ何時に修行僧が訪れても、成績表にずらりとAを並べた女子生徒がやるような笑顔で、料理と宿のもてなしをした。そうした献身を一万日以上も続けているのだ。だから彼女の暮らしを垣間見るたびに、私は自分の徳だけがまるで貯まっていないことに焦りを感じた。なぜなら私が十歳のときは遊戯王カードのことしか考えていなかったし、日が昇る前から起きるなんて遠洋漁業の漁師くらいだと信じていたからだ。
もちろん世の中には、そうした献身を世襲による自己犠牲だと非難する者がいるかもしれない。もっと好き勝手やればいいのにと揶揄する者がいるかもしれない。しかしそうした意見は、単に《自足すること》を知らない者のお節介に過ぎなかった。誰もが外の世界へ青い鳥を探し求めるなか、理子だけは変わり映えのない暮らしの内に、幸福の種をいくつも見つけることができたからだ。実際に彼女はいつも満たされた様子で、「あなたが落としたのは銀の斧ですか」と尋ねる泉の精霊のような話し方をした。私はもう十分に幸せだから、どうか貴方のことを祝福させてと言わんばかりに。
他人の幸福を心から喜べるタイプの人間が圧倒的に不足している時代なのか、彼女のもとには話を聴いてほしい者たちが絶えなかった。見ず知らずの人物がどこかで噂を聞きつけて、わざわざ話にやってきたりもした。だから理子は凪(なぎ)のような暮らしをしながらも退屈をしている暇はなかった。台風の目みたいな彼女をみるとこう思う。世界を面白くするのは、神の気まぐれではなく、我々の態度次第なんだと。
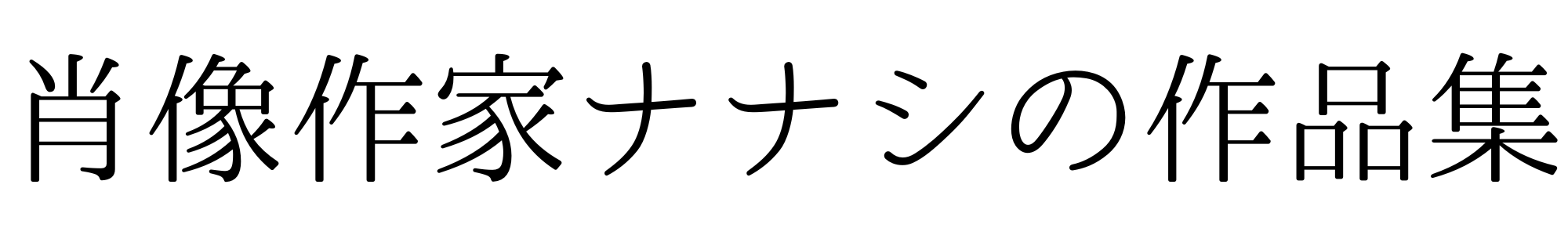
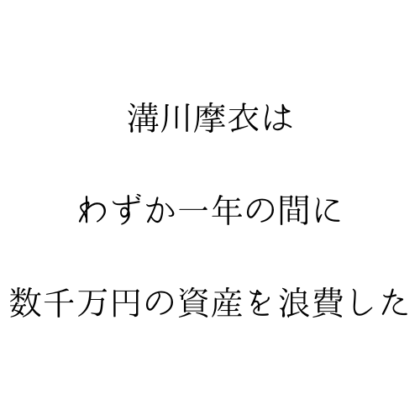

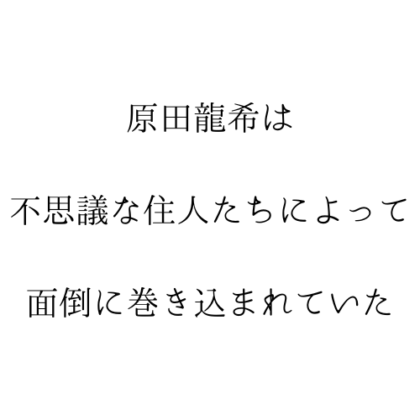
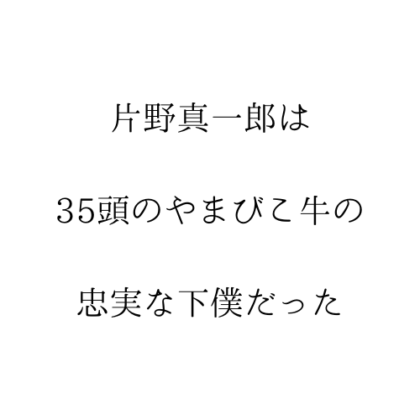
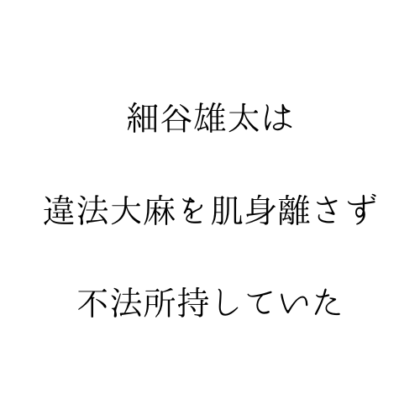
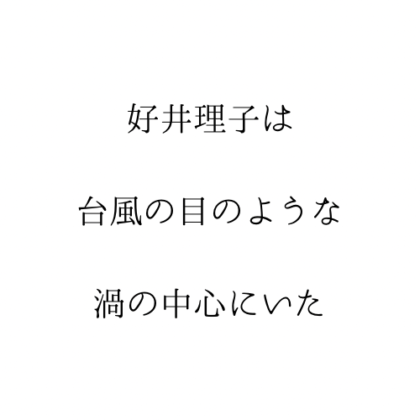
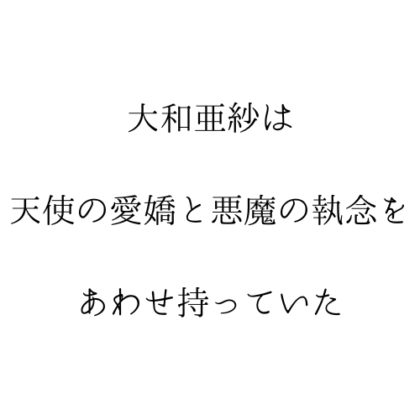
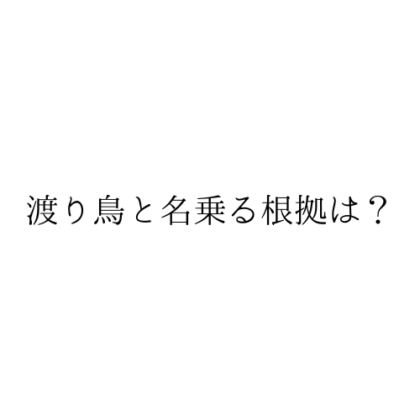

Leave a Reply