笠原悠仁は賞賛と叱責を受ける焼き鳥職人だった
笠原悠仁は、賞賛と叱責を等しく受ける、焼き鳥職人だった。
笠原の店は、訪れた客からふたつの対極的な評価を受けていた。レビューサイトに寄せられる投稿は、最高(5)か最低(1)のどちらかで、そこには中間というものが存在しなかった。最高でなければ最低、最低でなければ最高と、まるで判を押したみたいに票が分かれていた。褒め称える側の意見を覗くと、「究極」だの「至高」だの「絶頂」だの、焼き鳥屋に向けた言葉としては、いささか大袈裟な言い回しがみられたが、それに反発するかの如く、対立派の意見は厳しいものだった。「不愉快」「ストレス」「殴りたい」など、高級料理店には似つかわしくない言葉が投げられていた。
低い評価をつけた者の中で、味に文句を言うものはひとりもいなかった。寧ろその点については公平に評価していた。彼らはみな一様に、笠原の接客態度に物を申したいのだと訴えた。無愛想で高圧的、気を遣って仕方なく、注文をするたびに寿命が縮みますという証言もあった。写真を撮って本気で怒鳴られたという不憫な男性は、「彼の店でもし遅刻でもしようものなら、串で刺されるか、炭で焼かれるでしょう。」と注意を促す。
それでも笠原の店が高い評価を受け、予約の取れない名店として名を轟かせていたのは、彼の欠点を補って余りあるほど《火入れ》の技術が優れていたからだ。それぞれの部位において、焼き目には芸術的な趣があり、香りには哲学的な余韻があった。先付けひとつ取っても文句のつけようがなかった。舌の超えた食通でさえ、ひと串食べるごとに席を立って拍手をし、アンコールを唱えたくなる気持ちを抑えなければならなかった。コースが終わり、追加注文が許されると、客たちはお腹がはち切れるまで(あるいは笠原に追い出されるまで)注文を続けた。
そのような前評判を聞いていたので、私は死刑台に登るつもりで彼の店を訪れた。神戸の街の一等地、厳かな玄関に品の良い植栽、いかにもその道のプロという風体の主人。確かにそこにはある種の緊張感が漂っていた。しかしひとたび晩餐が始まると、研ぎ澄まされた鶏料理だけに意識が向かい、それ以外の情報(愛想や愛嬌がどうというの)は、気にかける余裕もなかった。特に笠原が焼き台に立ち、火入れをしている最中は、その表情があまりに真剣だったので、息を呑むのも憚られたくらいだ。たとえ酒の追加注文であったとしても、あの瞬間に声を発するなんて、弓道家が精神を統一して今まさに弓を放たんとしたときに、高速しりとりを始めるようなものだから。
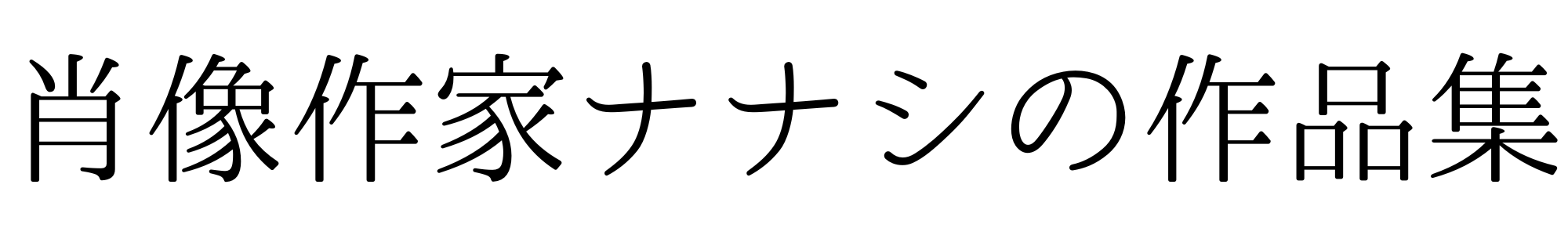
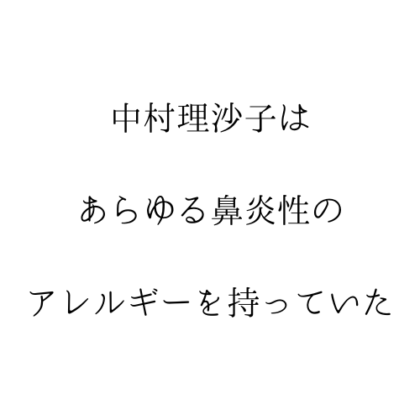
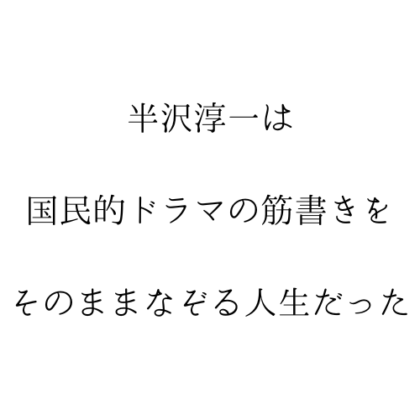
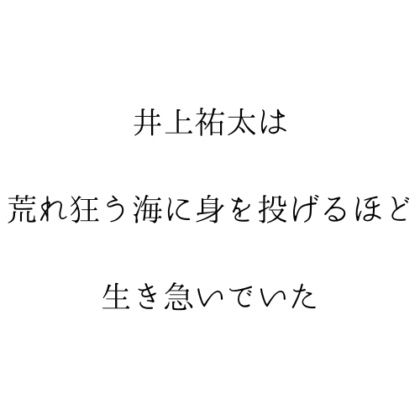
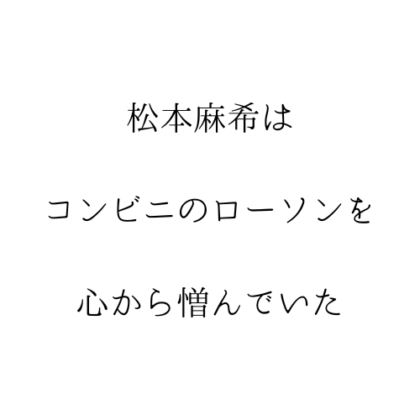

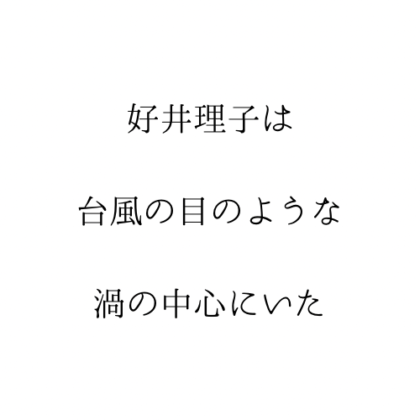
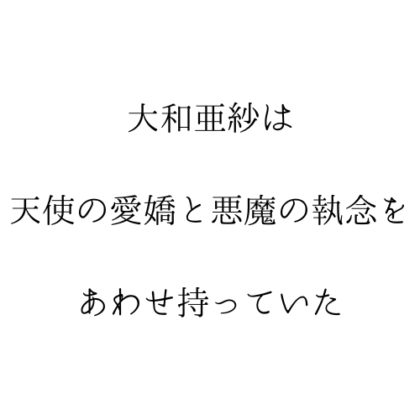
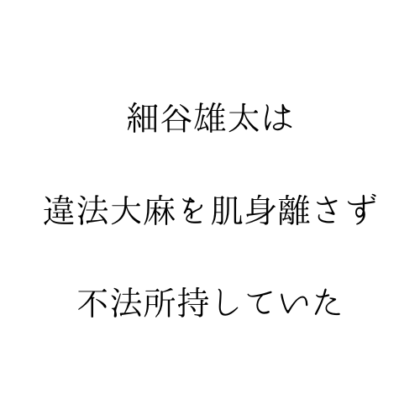
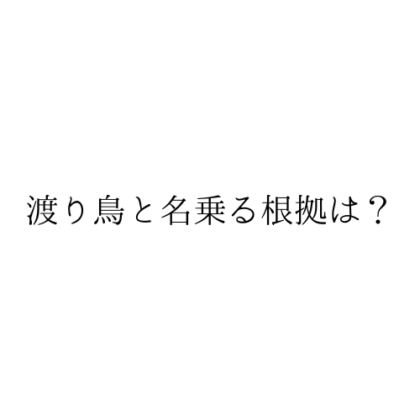

Leave a Reply