山下亮は好奇心に何度も殺されかけた
山下亮は、自らの好奇心によって、何度も殺されかけた。
会社を興して3ヶ月、山下の状況は最悪だった。口座の残高は182円で、売上の見通しもなく、来週には事務所の家賃と社員の給料を払わなければならなかった。ここ一週間、ほとんど何も口にしていなかったので、医学的にみればもう半分は死んでいるようなものだった。
しかし思い返してみれば、3ヶ月前もさほど状況は変わらなかった。手持ちの現金はわずかで、督促は鳴り止まず、取引先は壊滅的にゼロだった。創業時に雇った社員は、何十社も面接に落ち、今にも海に身を投げそうな学生だけだったし、なにを血迷ったのか、山下はその月に入籍も果たしていた。客観的にみれば、死ぬ前にせめてもの想い出を残そうとしているようだった。
念のため断っておくが、山下は決して頭の悪い人物ではない。むしろ熟練の棋士のようにおそろしく切れた。数学の学士を持っていたし、麻雀をさせればプロでも勝てなかった。高度なコンピューター言語も扱えたし、クラシック・ピアノも学年中の女子たちを虜にするくらいに上手く弾けた。問題は、彼の中にある《抑えられない好奇心》が、目に見えるリスクよりも、目に見えない可能性に賭けてみたくなってしまうことにあった。
さて、いよいよ支払いが不能になる日の前夜、山下は悪夢にうなされ一睡もできなかった。翌日、蜂に刺された野良犬のような顔で出社すると、あの社員が仕事の依頼を持ってきた。それは、真っ黒になったオセロの盤面を一手でひっくり返すような額の仕事だった。全ての支払いを済ませ、おまけにエアコンと冷蔵庫とウイスキーを買った。「僕たちは成功者だ」と社員が言い、山下はその言葉にいたく満足した。
彼らはとことん仕事を楽しみ、常に期待を上回るものを提供していたので、満足した顧客たちは次の顧客を紹介した。カレンダーをめくるたびに、依頼が増え、仲間が増え、働く環境が充実した。しかし平穏や安息を感じると、山下はときどき思いついたように、会社を倒産の危機に追いやるような次元のリスクを取った。せめて家族の反対があれば考え直したかもしれないが、あいにく彼の妻も一緒になって楽しんでいた。その度に周りの者は寿命を縮めたが、本当にダメになる寸前で《見えない何か》に救われ、受けた痛みの分だけ躍進した。
私からみた山下の生き様は、あらゆる技術を習得した熟練のボクシングの王者が、今なお新人ボクサーとノーガードで殴り合いをしているようだった。いいさ、どうせいつか灰になるなら、燃え尽きるまでやってやろうじゃないか、と。
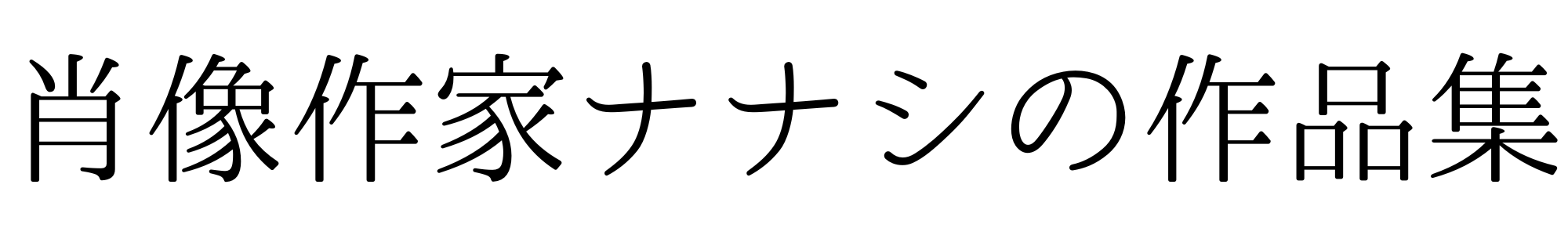
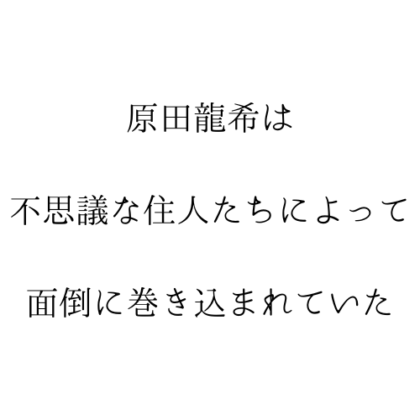
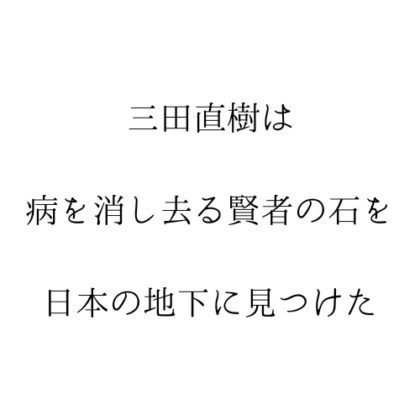
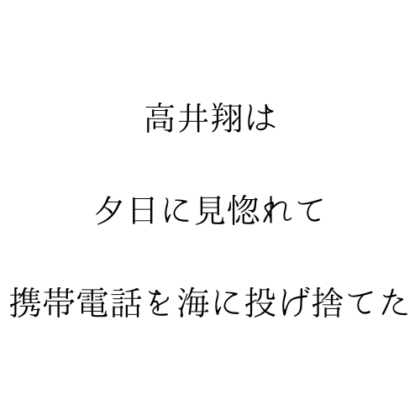
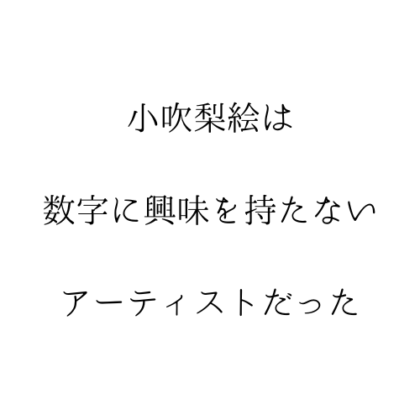
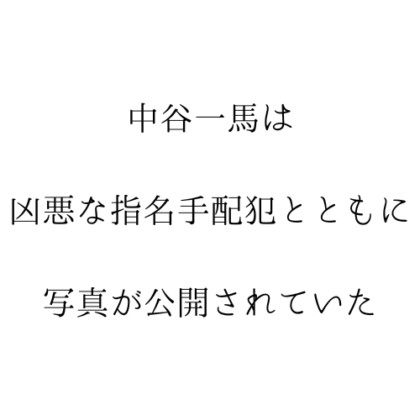
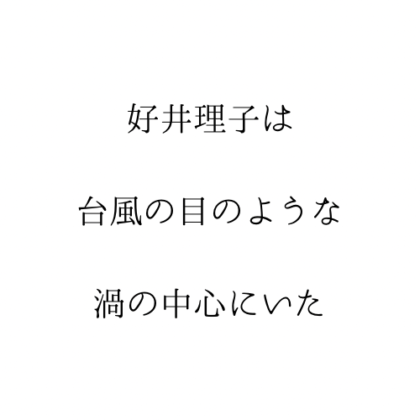
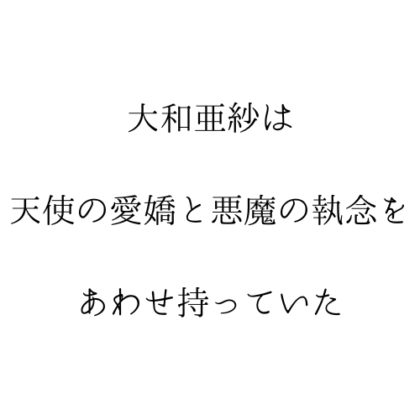
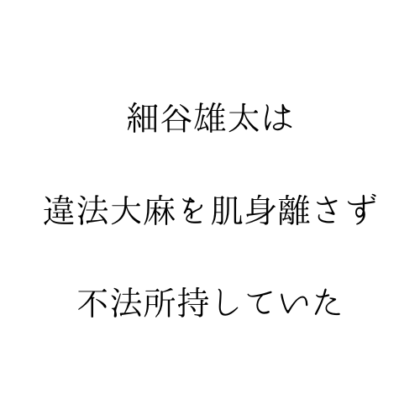
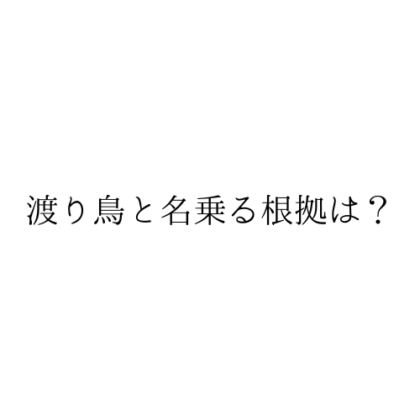

Leave a Reply