溝川摩衣は酒の誘いを冷淡に断り続けた
溝川摩衣は、いかなる酒の誘いも冷淡に断り続けた。
摩衣は、相手が何処の誰であろうと酒の誘いはきっぱりと断った。理由はただひとつ、とてつもなく弱かったからだ。その弱さはちょっとした評判になるくらいのもので、お猪口の酒はおろか、モロゾフのウイスキー・ボンボンをふた粒も与えれば、たちまちちびまる子ちゃんみたいに頬を赤らめた。しかし生憎なことに、彼女はどこからどう見ても酒飲みに見えた。言動はこざっぱりと淡白で、声にはアルトの低さがあり、顔には「お酒が大好きです」と書いてあった。甘いものよりは辛いものを好み、お歳暮の時期には、唐墨(からすみ)や海鞘(ほや)、海鼠腸(このわた)なんかを嬉しそうに選んでいた。だから彼女が飲めないと断っても言葉通りに受け取る者はいなかった。
申し訳ないと言いながらも、本心ではお酒への強い興味があった。彼女がお洒落だと感じる店は、たいていワインやカクテルを嗜むことを前提にした場所だったし、和食やフレンチのコースにお茶や水を合わせるというのも、どことなく決まりが悪いように感じていたからだ。ペアリングやマリアージュという言葉が何を指しているのかもわからないし、飲めないならと入店を断られることも少なくはなかった。呑んだ呑まれたという話を訊くたびに、子どもが魔法の世界に抱くような憧れを感じるようになった。お酒を好きなように飲めるというのは、おそらくは空を飛ぶことの次に楽しいのだろう。
積年の感情が抑えられなくなった摩衣は、酒飲みの門戸を叩いて稽古をつけてもらうことにした。どれだけ辛い修行だとしても、私は絶対に弱音を吐かないしもどさない、だから強くして欲しいと彼女は熱意を伝えた。よろしい、そこまで言うなら教えて差し上げよう。酒飲みになるための原理は単純で、筋肉をつけるのと同じように少しずつ負荷をかけていくというものだった。まずは鼻腔にアルコールを慣らすために、ワインを使った匂いの訓練から始まった。初日はコルクを嗅ぐだけで眩暈を患ったが、少しずつそれに慣れると、翌週にはワインの香りをビニール袋に閉じ込め、口と鼻を当てて呼吸をする訓練が始まった。不良少年がシンナーを吸うあのやり方だ。それを春の間続けると、摩衣はもう頭からシャンパンを浴びても動じないようになった。夏からは舌を、秋からは肝臓の訓練が始まった。
厳しい冬を乗り越えて、彼女が修行から戻ってきた。右手には一升瓶の芋焼酎『魔王』を、左手には『獺祭磨きその先へ』を持ち、早く誰か飲みに付き合ってくれと走り回っていた。やれやれ今度は彼女が断られる番だろう。
コメント3件
袋に向かってスーハーするように指示された時には、酒豪に師事するという自分の選択を後悔しかけたものです。
しかし結果的に“お酒好き”というスキルセットは、どんな社交ツールより有効に機能しているようです。顔とスキルが一致し、なにかいい方向に全部が動いている気がします。
唯一困ったことといえば、エンゲル係数が上がったことでしょうか。なぜ“日本酒”という単語は、ここまで心踊らせてくれるのでしょうか。つい手が伸びてしまいます。
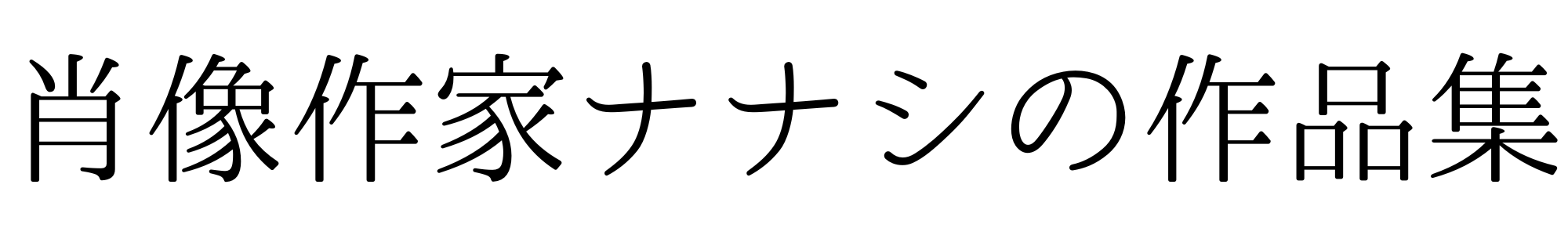
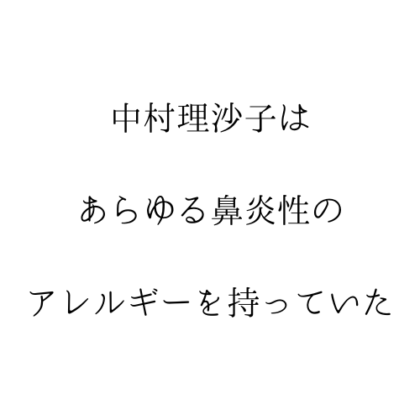

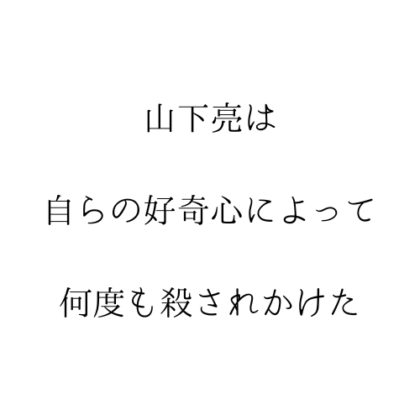
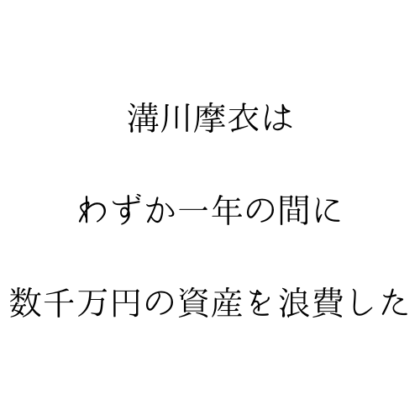
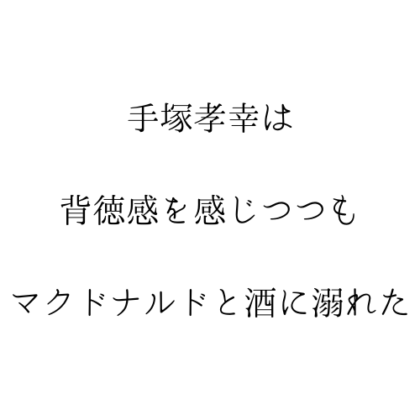
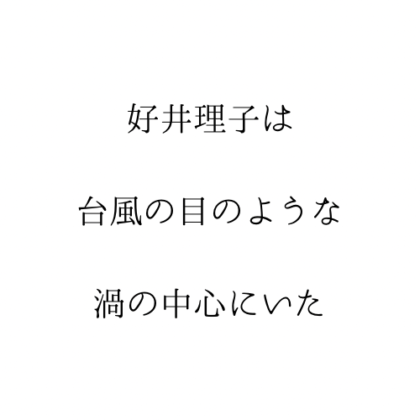
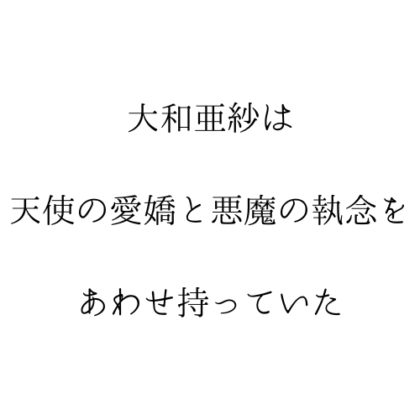
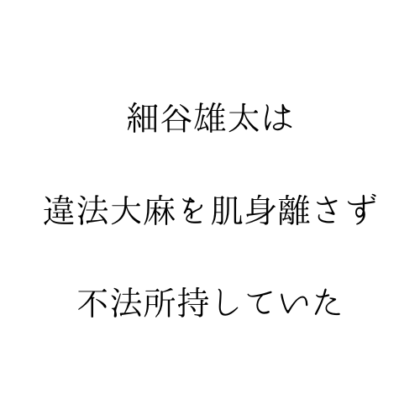
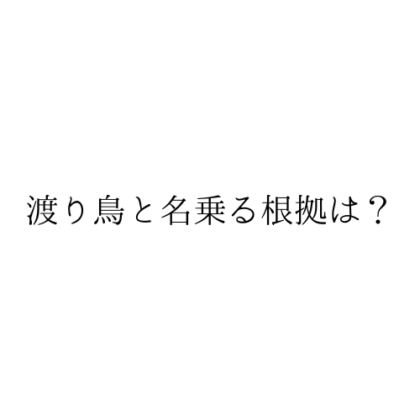

先日の『寿司と蕎麦の和の饗宴』でお会いした際は、稽古の成果がばっちりだったんですね。日本酒を嗜む姿から、下戸であったことは微塵も感じられませんでした。一升瓶を用意しておくので、朝まで語り合いたいものです。