林雄次郎の夢は役場で勤めることだった
林雄次郎の夢は、町役場で定年退職まで勤めあげることだった。
幼い頃、周りの子どもたちが、セリエAのスター選手やメジャーリーガーに憧れる中、こと雄次郎だけは、まるで勅命を預かった実直な武士のように、生まれ育った町に奉仕することこそが、今世の使命だと感じていた。
もっとも、初めは漠然とした地元愛からだったが、小中高と教養を身につけるたび、その意志は確かなものとなり、大学を卒業する頃には、地熱と圧力によって押し固められた金剛石(ダイヤモンド)の如く純然たるものになった。
就職活動における第一志望から第三志望は、すべて町役場と書いた。雄次郎にそれ以外の選択はなく、そこには留保も条件もなかった。譲歩も妥協も代替も存在しなかった。「けれども」や「あるいは」が入り込む余地さえ無かった。そして彼は見事に勝ち取った。
同級生たちはみな、給料の高い企業から順に志望したため、ほとんどの者が上京したが、雄次郎だけは躊躇いなく故郷へ回帰した。産卵のために海から川に向かう鮭や鱒のように。あるいは脂を蓄えた戻りガツオのように。
彼の地元は、それこそ特筆すべきことは自然くらいしかなかったので、上京した大学の同期たちは、雄次郎を心配した。彼らは(高給取りの代名詞である)総合商社や外資系コンサルタントに就職をし、煌びやかな生活を待ち望んでいたため、田舎に留まるなんて心外という様子だった。
しかし、雄次郎の側もまた、彼らのことを心配していた。彼らの仕事の内容は何度聞いても、木魚のビートに合わせる僧侶のお言葉くらいに実態が見えてこなかったし、彼らの(想像力豊かだった)頭は、給料と出世のことしか考えていないように思えたからだ。
実際に数年後の彼らは、まるで判を押したように(そして雄次郎が予想した通り)、港区のマンションに住み、高価な時計を持ち、休日にはゴルフをしていた。アサインやショートノーティス、キャリアアップといったわけのわからない言語を話し、常により好条件の転職先を探していた。
雄次郎は不思議に思った。「自分は大衆とは違うんだ」と金目の物を求めることで、結局みんなと同じになっていることに、頭の切れる彼らがなぜ気づかないんだろう。死の淵に持っていけるものは、他人が造った消費物ではなく、愛情に溢れた思い出だけなのに。
生まれてから愛を与えてくれた町に、愛をもってお返しすることが、雄次郎が求めている善い生き方だった。そんな彼が今日も窓口で奉仕をしてくれていると思うと、(同じ町に生まれた者として)涙が出てくるものだ。
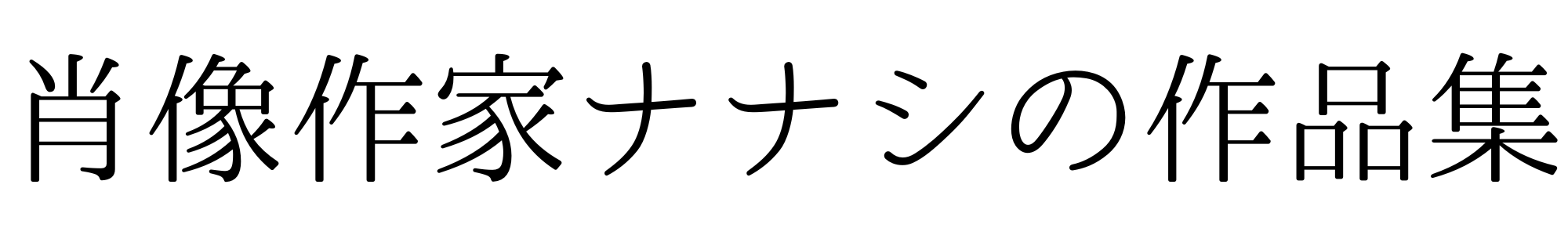
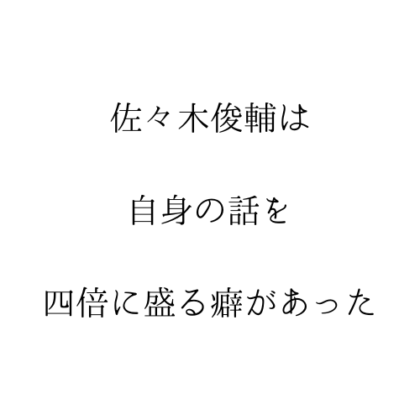
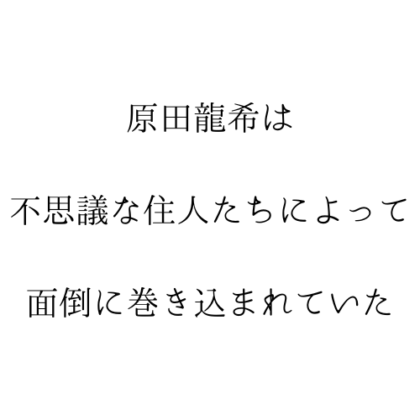
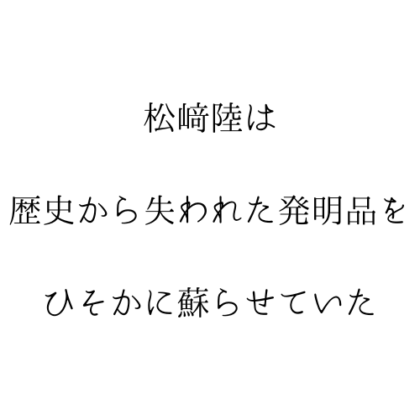
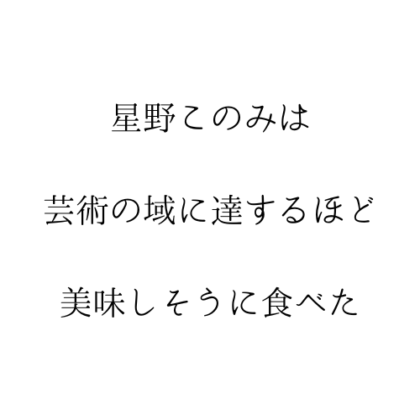
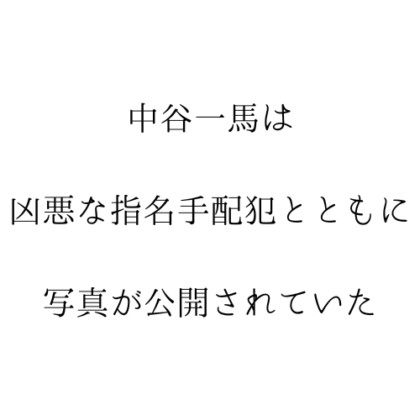
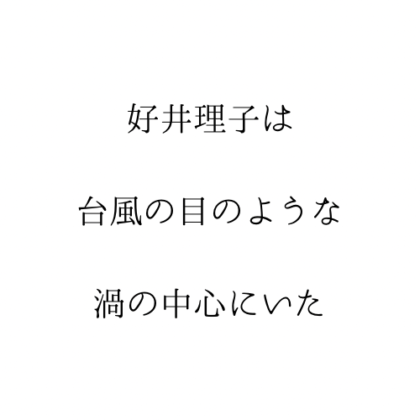
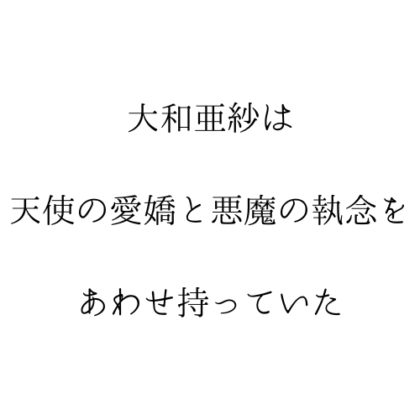
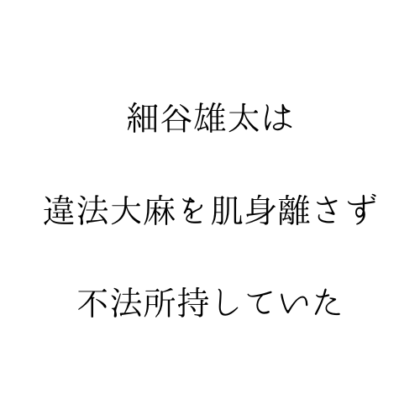
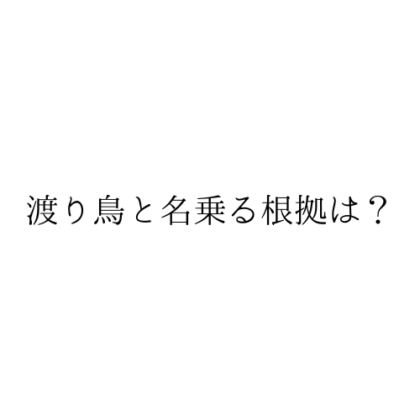

Leave a Reply